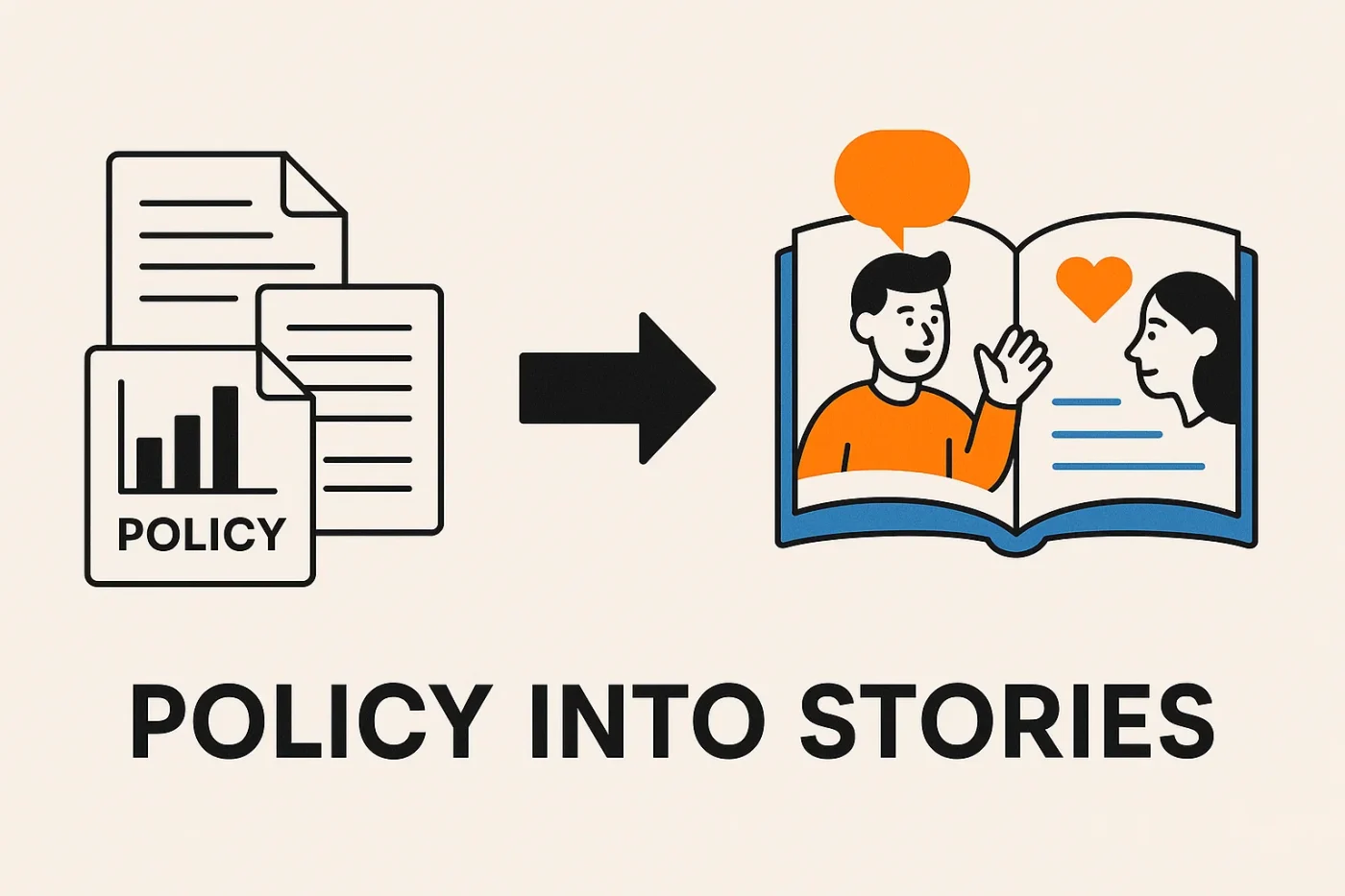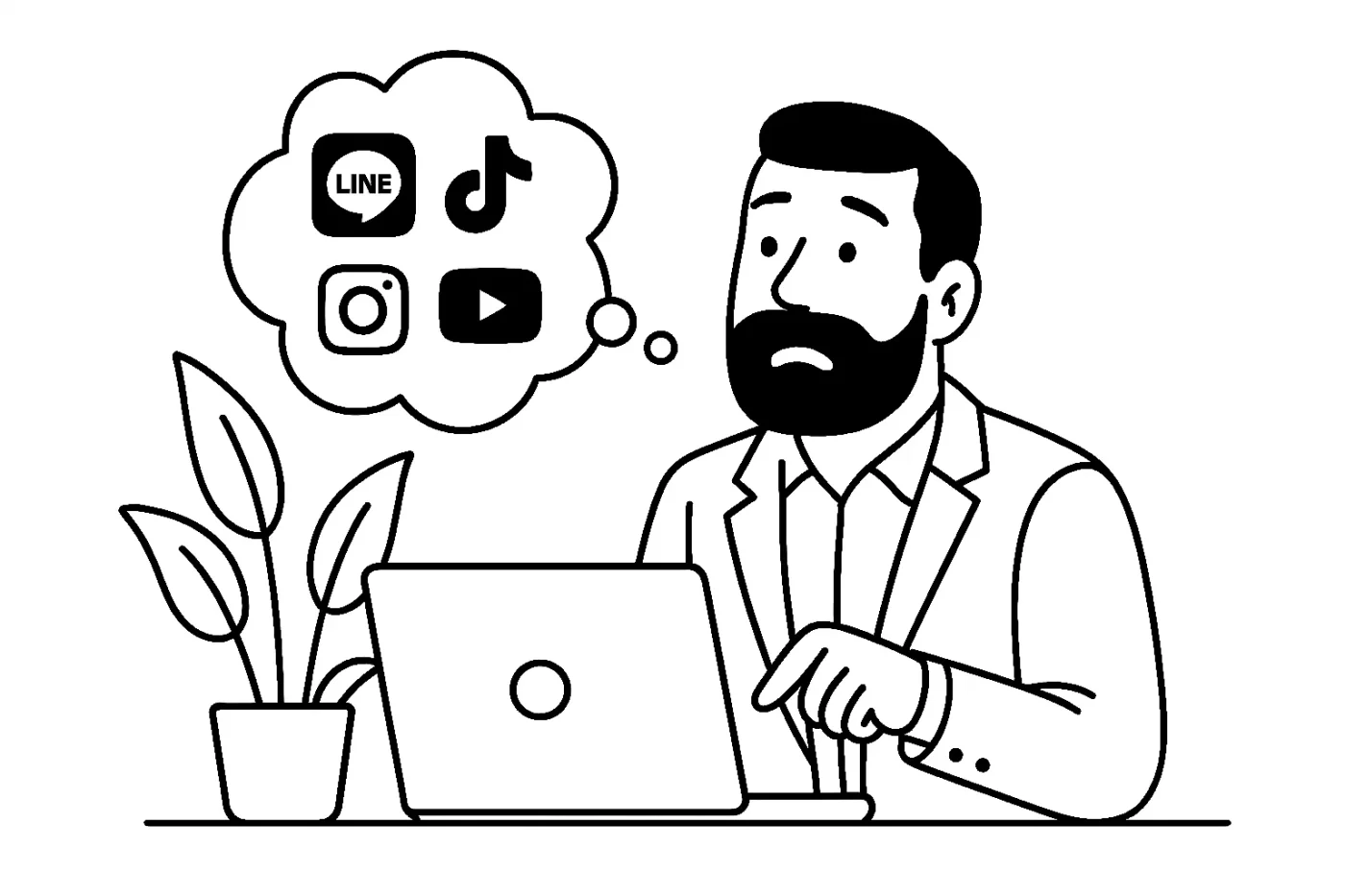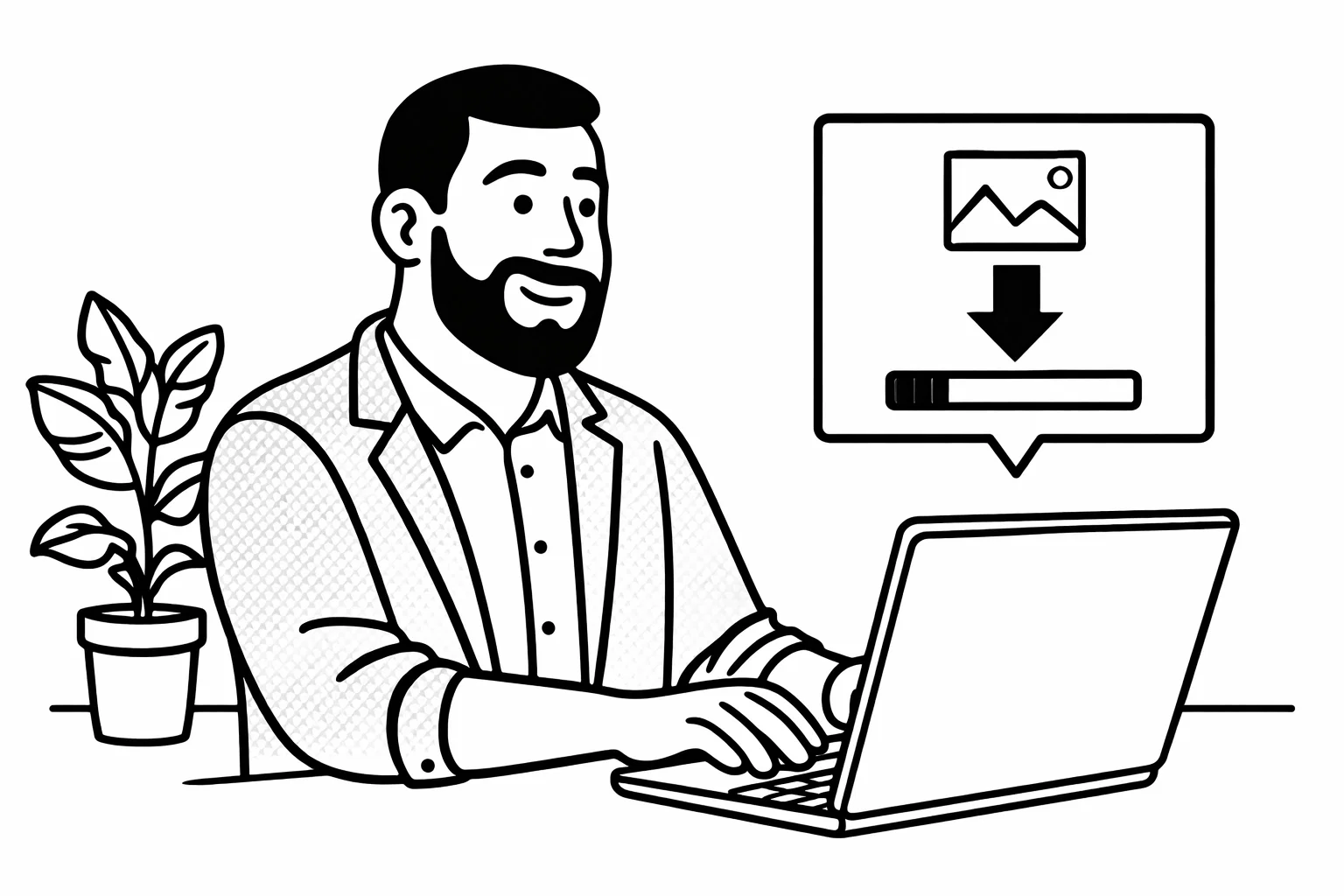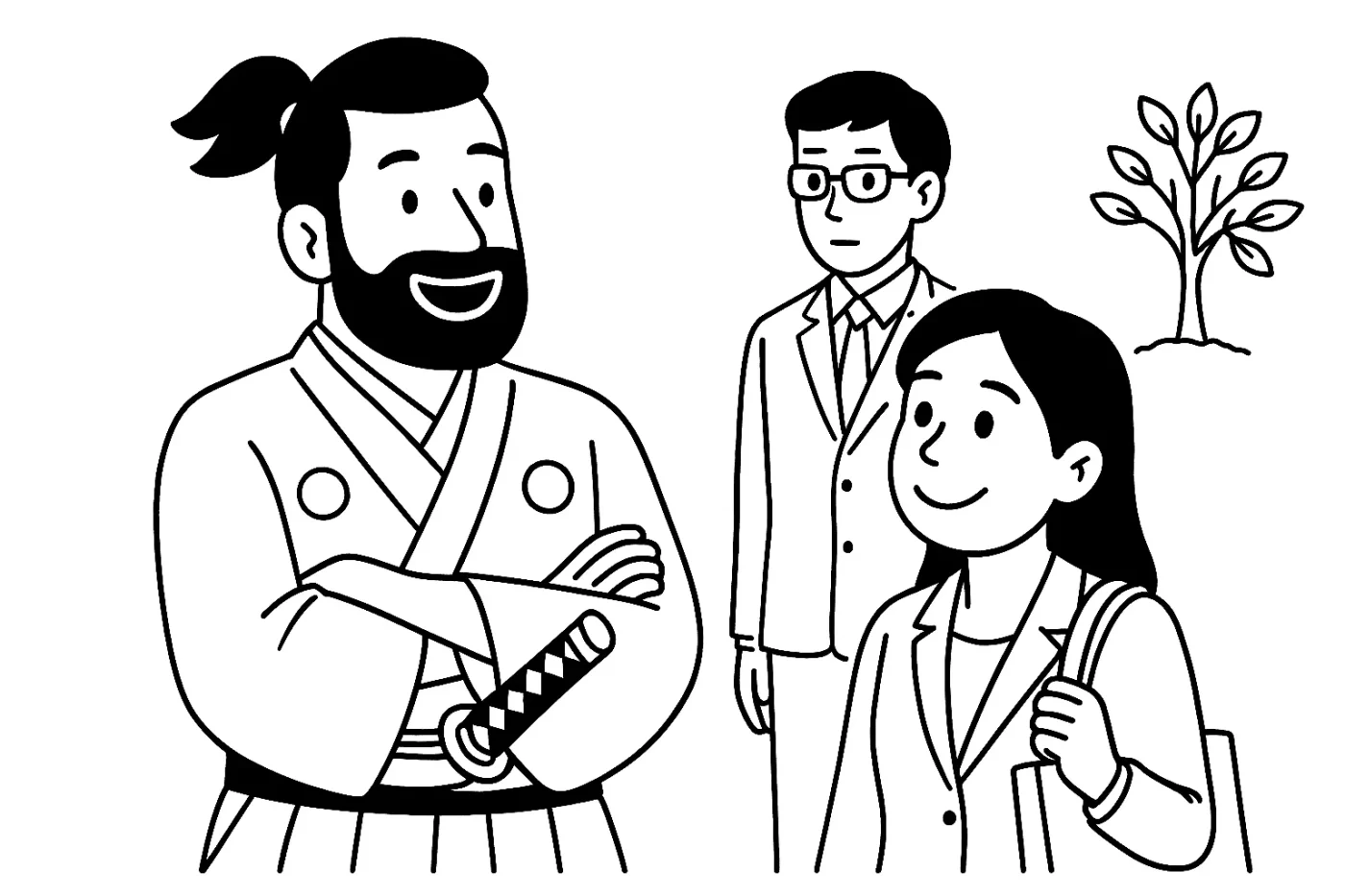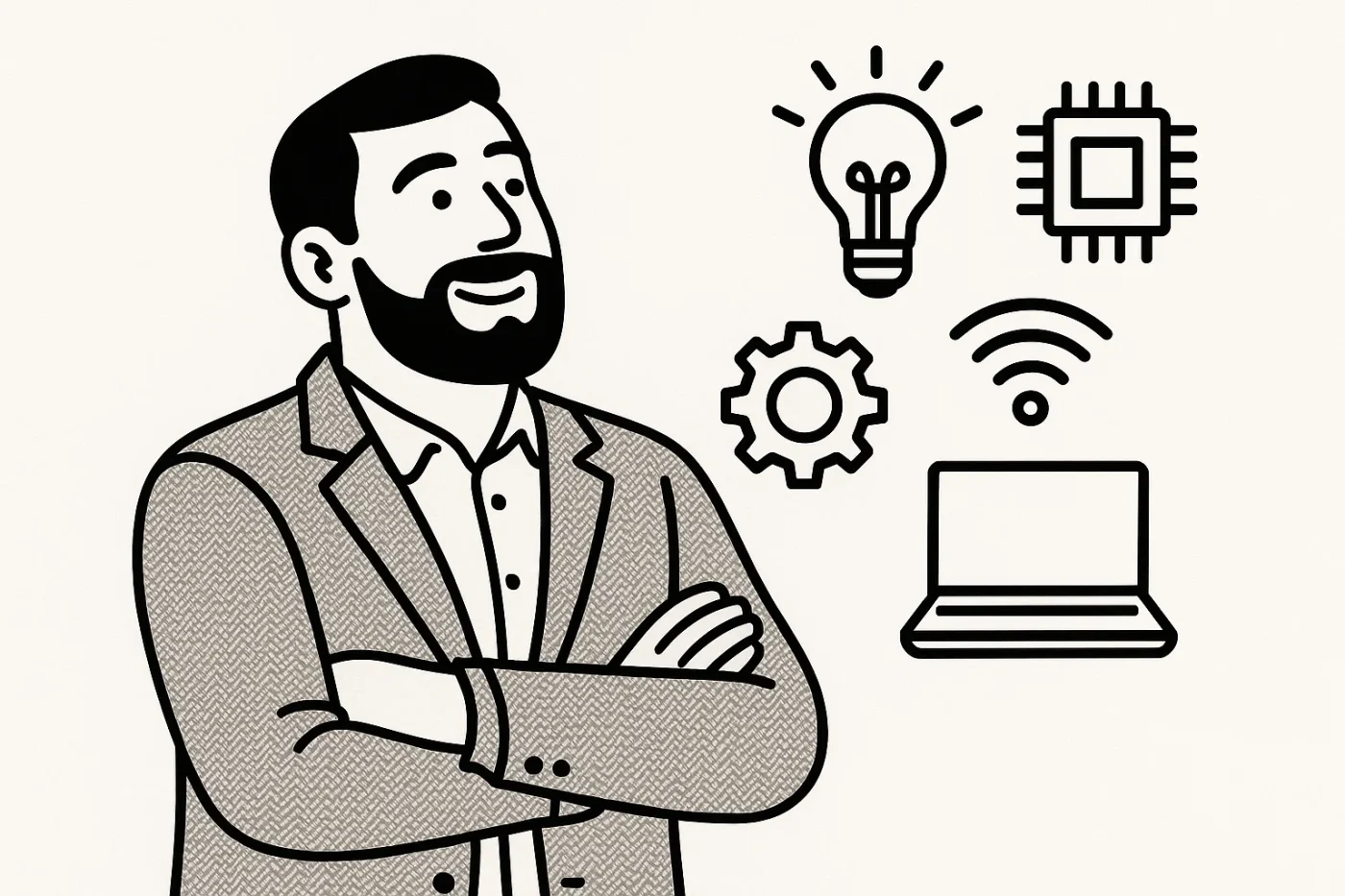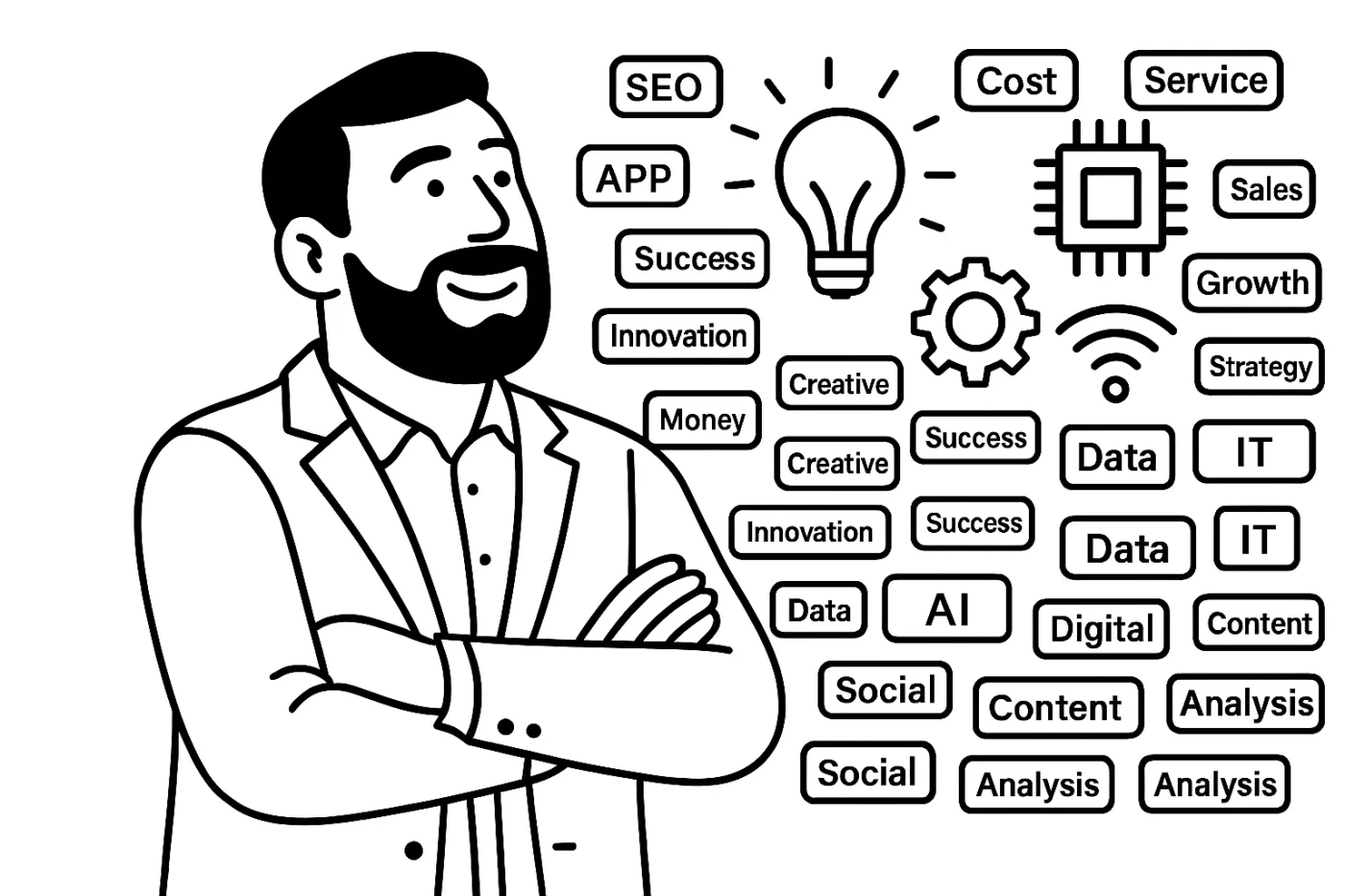政策エンタメの定義
「政策を面白くする」のではなく、「面白い物語の中に政策を埋め込む」。
これが、私たちが提唱する“政策エンタメ”の考え方です。
政策エンタメ(Policy Entertainment)とは、社会課題の解決策を娯楽小説の形式で提示する新しいコンテンツジャンルです。
従来の政策論文や白書では専門家にしか伝わらなかった複雑な制度設計を、感情移入できるキャラクターとドラマチックな展開によって一般読者に届けます。読者は「面白い」と感じながら政策リテラシーを獲得し、社会変革への当事者意識を持つことができます。
なぜ今、政策エンタメが必要なのか
従来の政策発信の限界
日本では毎年、数千本の政策論文やレポートが発表されています。しかし、その大半は専門家以外に読まれることはありません。
従来の政策発信が抱える3つの問題:
- 専門用語の壁: 一般市民には理解できない
- 感情の不在: データだけでは人は動かない
- 当事者意識の欠如: 「自分には関係ない」と思われる
結果として、優れた政策提言があっても社会実装に至らない。これが日本の政策形成における最大の課題でした。
物語の力を活用する
人類は何千年も前から、物語によって知識や価値観を伝承してきました。
- 寓話は教訓を伝え
- 神話は世界観を共有し
- 小説は時代精神を表現してきた
政策エンタメは、この「物語の力」を現代の政策形成に応用します。
データと論理は物語の中に組み込まれ、読者は主人公と共に課題を発見し、解決策を模索し、実現の喜びを味わいます。読み終わった後、読者の中には「この政策、必要だ」という確信が生まれています。
政策エンタメの構造
政策エンタメは、以下の3層構造で成り立っています。
第1層:エンターテインメント(表層)
- 感情移入できるキャラクター
- ドラマチックな展開と葛藤
- ページをめくる手が止まらない物語
読者はまず「面白い小説」として楽しみます。
第2層:政策提言(中核)
- 実現可能な制度設計
- データに基づくシミュレーション
- 行動経済学などの理論的裏付け
物語の中に、実際に機能する政策が埋め込まれています。
第3層:社会変革(深層)
- 読者の政策リテラシー向上
- 社会課題への当事者意識の醸成
- 実際の政策実装への機運
読後、読者は「自分にも何かできるかもしれない」と感じます。
従来手法との比較
政策論文経済小説政策エンタメ主目的専門家への提言娯楽政策の社会実装読者層研究者・官僚一般読者一般読者〜政策立案者内容理論とデータドラマと人間関係政策提言+ドラマ実現可能性高いが読まれない低いが面白い高く、かつ面白い社会的影響限定的一時的持続的・実装可能
政策エンタメは、政策論文の実現可能性と、経済小説の娯楽性を融合させた新ジャンルです。
実証事例:地域創生リーグ
政策エンタメの第1作として、「地域創生リーグ〜地方と都会の逆転劇〜」(全18章)を執筆しました。
作品概要
物語: 財政破綻した北海道の夕焼市。父の遺言を胸に帰郷した小林拓也が、東京の豊かな自治体(湊戸区)からの支援を受けて街を再生させる物語。
政策提言: 全国1,741自治体を財政状況に応じて5つのリーグに分類し、豊かな自治体が厳しい自治体を支援する「地域創生リーグ制度」を提案。
理論的裏付け:
- プロスペクト理論(マイナポイントの心理効果)
- 同一視バイアス(交流イベントによる共感醸成)
- ホーソン効果(注目による成果向上)
実証事例:母屋の約束
政策エンタメの第2作として、「母屋の約束」(全15章)を執筆しました。

物語: 築90年の母屋で交わされた対話から生まれた、少子高齢化問題への提言。実業家2人が「祖父母育て支援」という新しい家族モデルを構想する物語。
政策提言: 親が祖父母に養育費を支払い、税制で控除する「祖父母育て支援制度」を提案。
理論的裏付け:
- 世界の事例(中国、アメリカ、南欧)
- 国防問題としての少子化対策
- 世代間の役割分担の最適化
政策エンタメの書き方
政策エンタメを創作するには、以下の5つの要素が必要です。
1. 実現可能な政策設計
- 単なる理想論ではなく、実際に機能する制度
- データに基づくシミュレーション
- 財源・実施体制・評価指標の明確化
2. 感情移入できるキャラクター
- 読者が応援したくなる主人公
- 現実的な葛藤と成長
- 多様な視点を持つ登場人物
3. データと感情の黄金比率
政策エンタメにおける理想的なバランスは 感情7:データ3
- 感情が多すぎると説得力に欠ける
- データが多すぎると退屈になる
物語の流れの中で、必要なタイミングで必要なデータを提示することが重要です。
4. リアルな対立構造
- 財務省 vs 総務省
- 都市住民 vs 地方住民
- 理想主義者 vs 現実主義者
現実の政策形成には必ず抵抗勢力が存在します。その対立をリアルに描くことで、物語に緊張感が生まれます。
5. 現場に行く—感情が政策の種になる
優れた政策エンタメは、データから生まれません。 現場で感じた「やるせなさ」から生まれます。
『地域創生リーグ』の著者は、夕張市を訪れたとき、こう感じました。
「最盛期に12万人いた町が、こうなってしまうんだな。理由はわかる。でも、何ともやるせない。」
この「やるせなさ」が、種になりました。
データだけを見ていたら、「人口減少率-93%」「財政再生団体」という数字で終わっていたでしょう。
しかし、現地に行き、廃墟を見て、それでも生活している人々を見て、感情が動いた。
その感情を言語化するために、旅ログを書きました。旅ログを書くことで、「引っかかり」が心に残りました。そして、その引っかかりが、政策の種になりました。
政策エンタメを書きたいなら、まず現場に行ってください。そして、感じたことを、正直に書いてください。
感情が、政策を生み、政策が、物語を生み、物語が、社会を動かします。
政策エンタメがもたらす3つの価値
1. 政策リテラシーの向上
読者は娯楽を楽しみながら:
- 政策形成のプロセスを理解
- データの読み方を学習
- 社会課題への関心を高める
2. 民主主義の深化
多くの市民が政策を理解できれば:
- より質の高い政治的議論が可能に
- ポピュリズムへの抵抗力が増す
- 政策の社会実装がスムーズになる
3. 政策立案の革新
政策立案者にとっても:
- 国民への説明ツールとして活用可能
- 制度設計の思考実験として機能
- ステークホルダーの合意形成を促進
政策エンタメは、書き手・読者・社会の三方良しを実現します。
政策エンタメの可能性
政策エンタメは「地域創生」「少子高齢化」だけにとどまりません。
今後展開可能なテーマ
- 税制改革: 累進課税の再設計
- 教育改革: 公教育の選択制導入
- 年金改革: 世代間の公平性確保
- 気候変動: カーボンプライシング制度
- 医療改革: 予防医療へのシフト
- 働き方改革: 副業・兼業の促進制度
すべての社会課題は、政策エンタメの題材になり得ます。
政策エンタメが変える未来
10年後、こんな世界を想像してみてください:
- 国会図書館に「政策エンタメ」専門コーナーが設置される
- 大学の政策学部で政策エンタメが必修科目になる
- 官僚が政策を説明するとき、まず政策エンタメ小説を配布する
- 選挙前、各政党がマニフェストを政策エンタメ化して発表する
政策が「専門家だけのもの」から「みんなのもの」になる。
それが、政策エンタメが目指す未来です。
この装置が機能しない状況
この「政策エンタメ」という手法は、万能ではありません。
装置が機能する条件:
- 実現可能な政策が設計できる
- 物語として成立する題材がある
装置が機能しない状況:
- 政策が複雑すぎて物語化できない
- データが不足している
こういった状況では、政策エンタメは機能しません。従来の政策論文の方が適している場合もあります。
まとめ:物語で社会を変える
政策エンタメは、3つの問いに答えます:
- なぜ優れた政策が実現しないのか? → 伝え方の問題
- どうすれば市民が政策を理解できるのか? → 物語化
- 政策をどう社会実装するのか? → 共感の醸成
データは人を説得するが、物語は人を動かす。
私たちは今、この新しいジャンルの創世記にいます。政策エンタメという概念が広がれば、日本の政策形成は大きく変わるでしょう。
論文では届かなかった人々に、物語で届ける。それが、政策エンタメの使命です。
結果的にそうなったら面白い。
ならなかっても(今)面白い。
多分これからも面白いかなと思える。
それ以上何も求めるものない。
政策エンタメ第1作「地域創生リーグ〜地方と都会の逆転劇〜」は、dramawork.jpで全編公開中です。
政策エンタメ第2作「母屋の約束」も、dramawork.jpで全編公開中です。
政策エンタメ第1作「理想の値段~28の声が問う、自治の未来~」は、dramawork.jpで全編公開中です。
「政策エンタメ」の概念は、有限会社ビーアイティー(BIT)が提唱する「概念創造型マーケティング」の実践手法のひとつです。