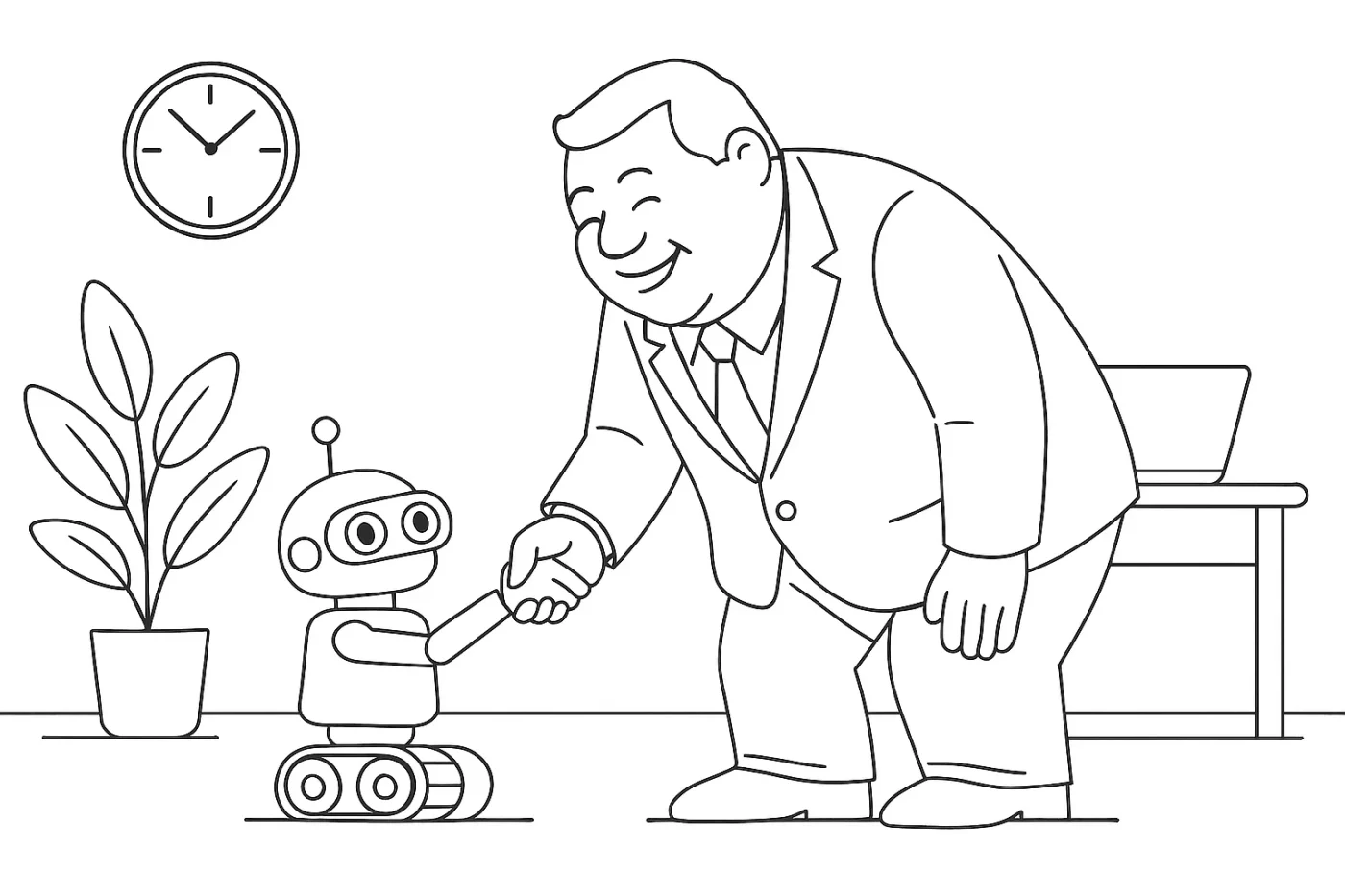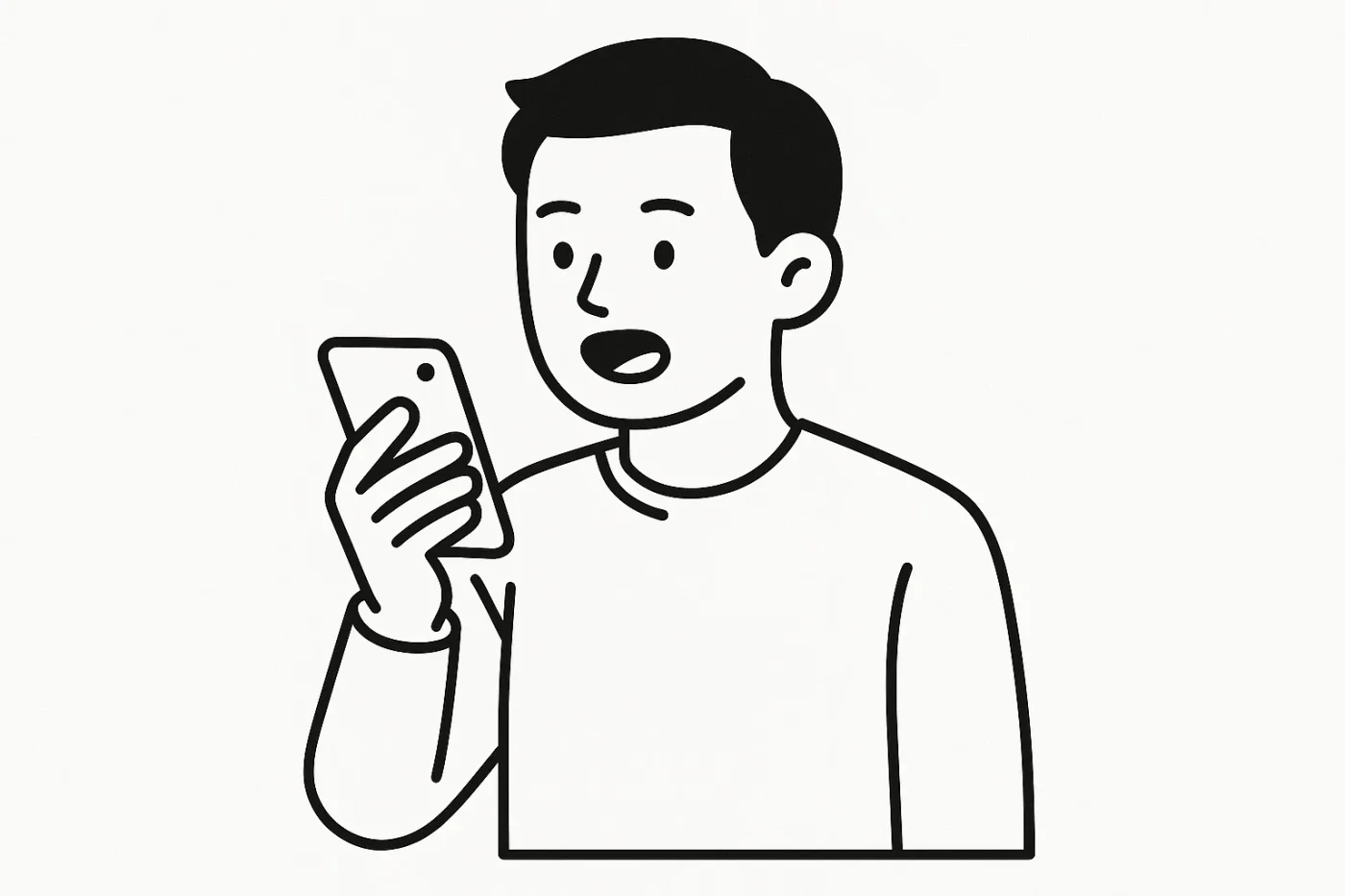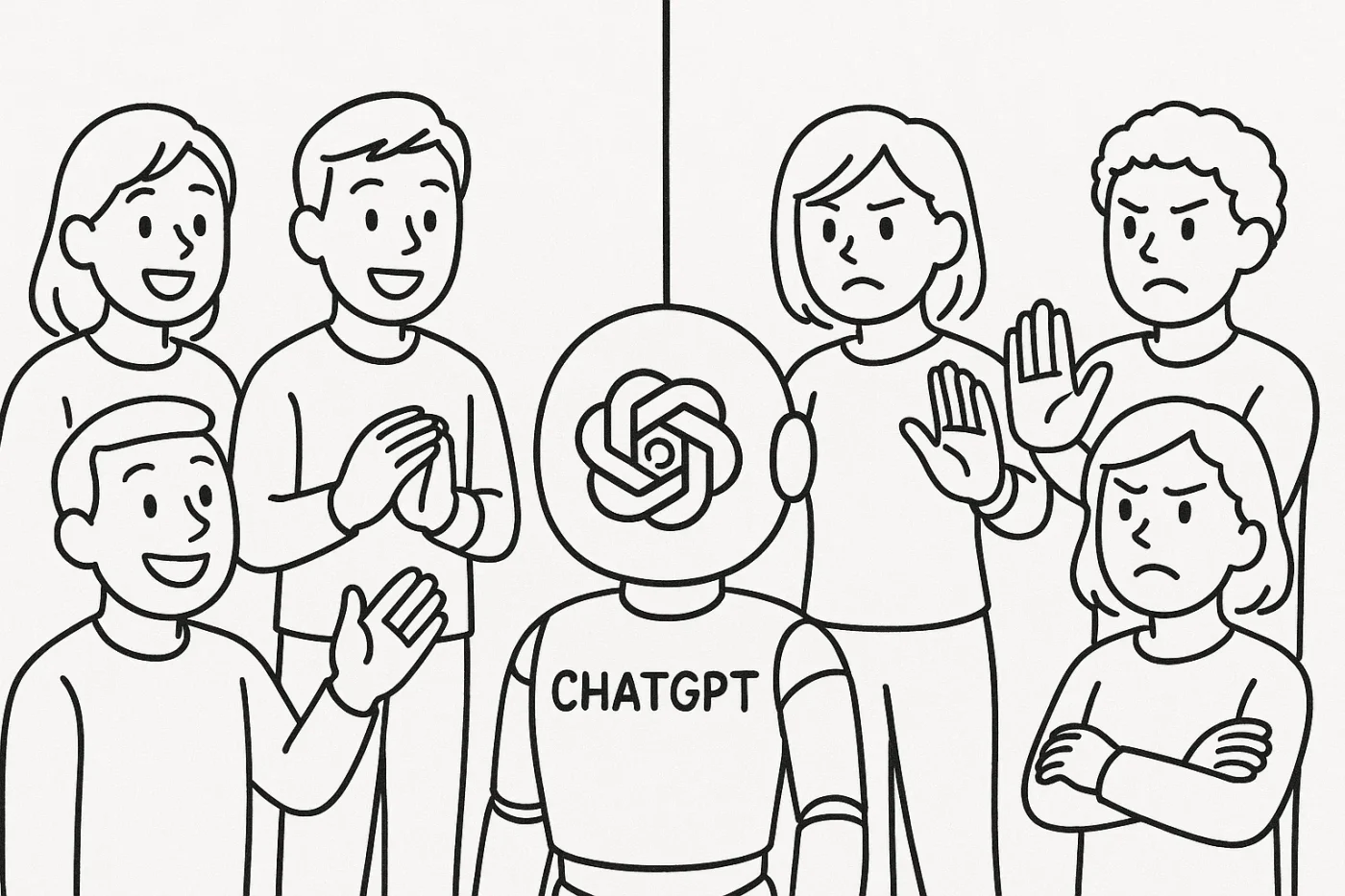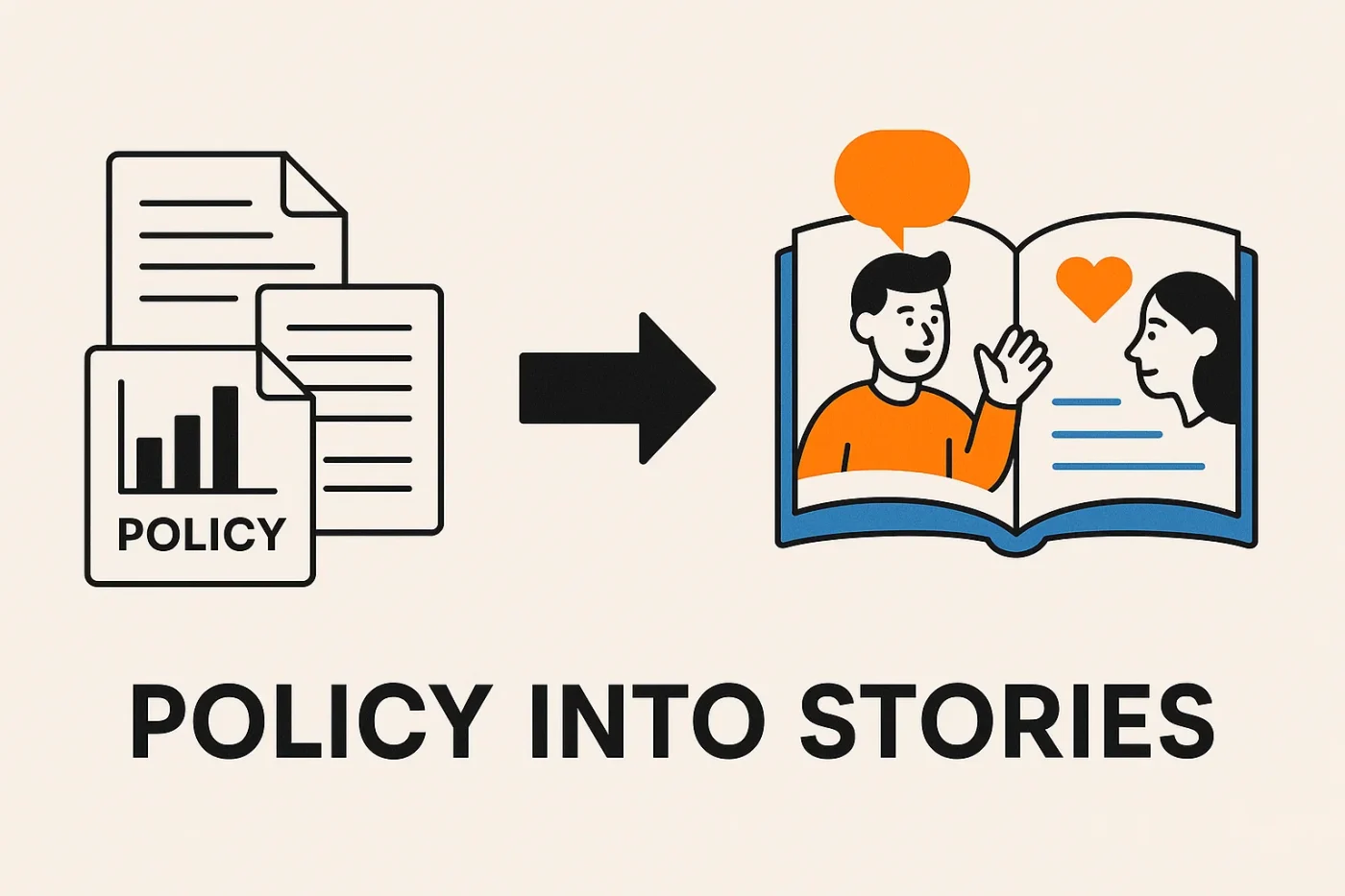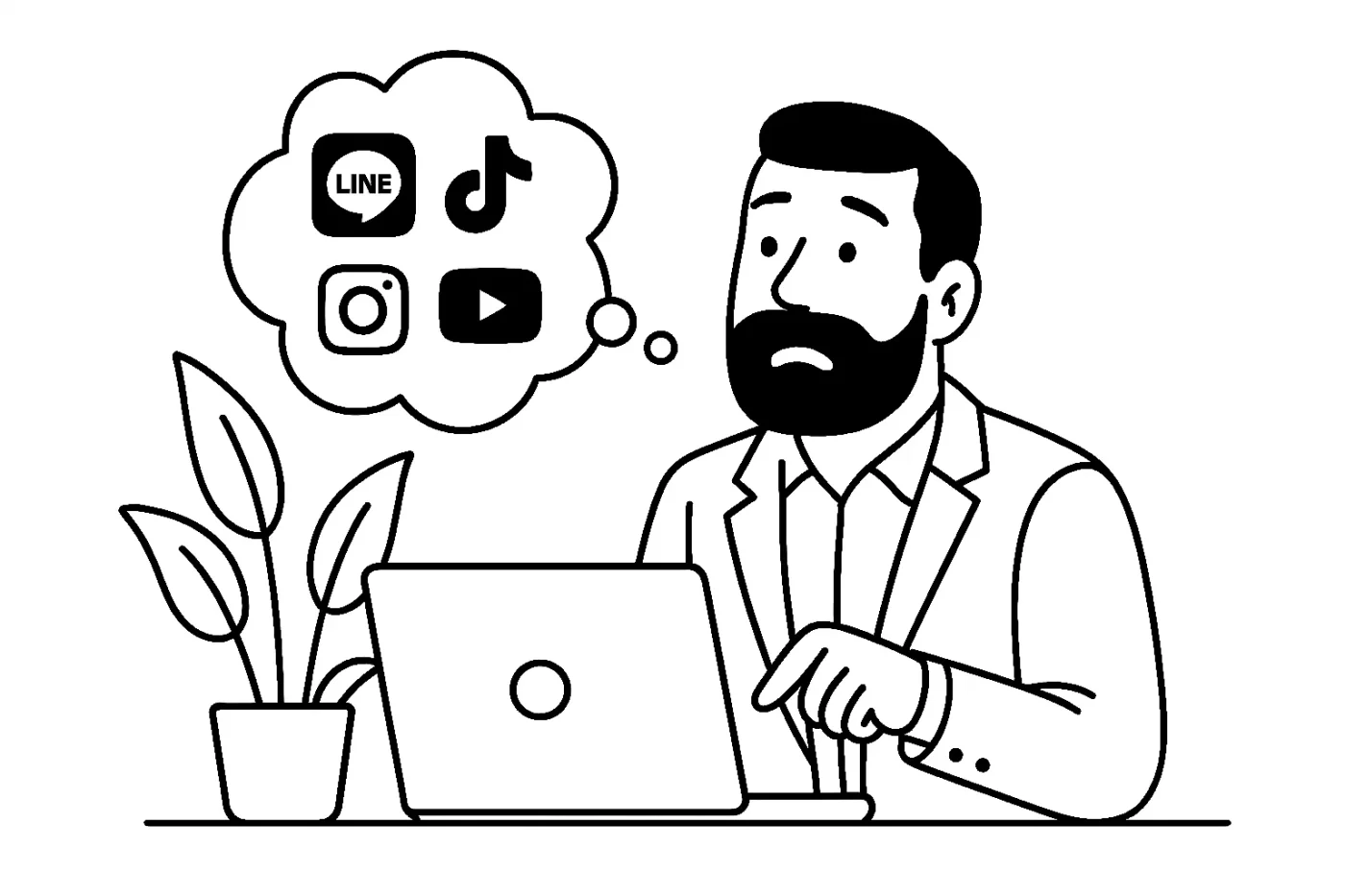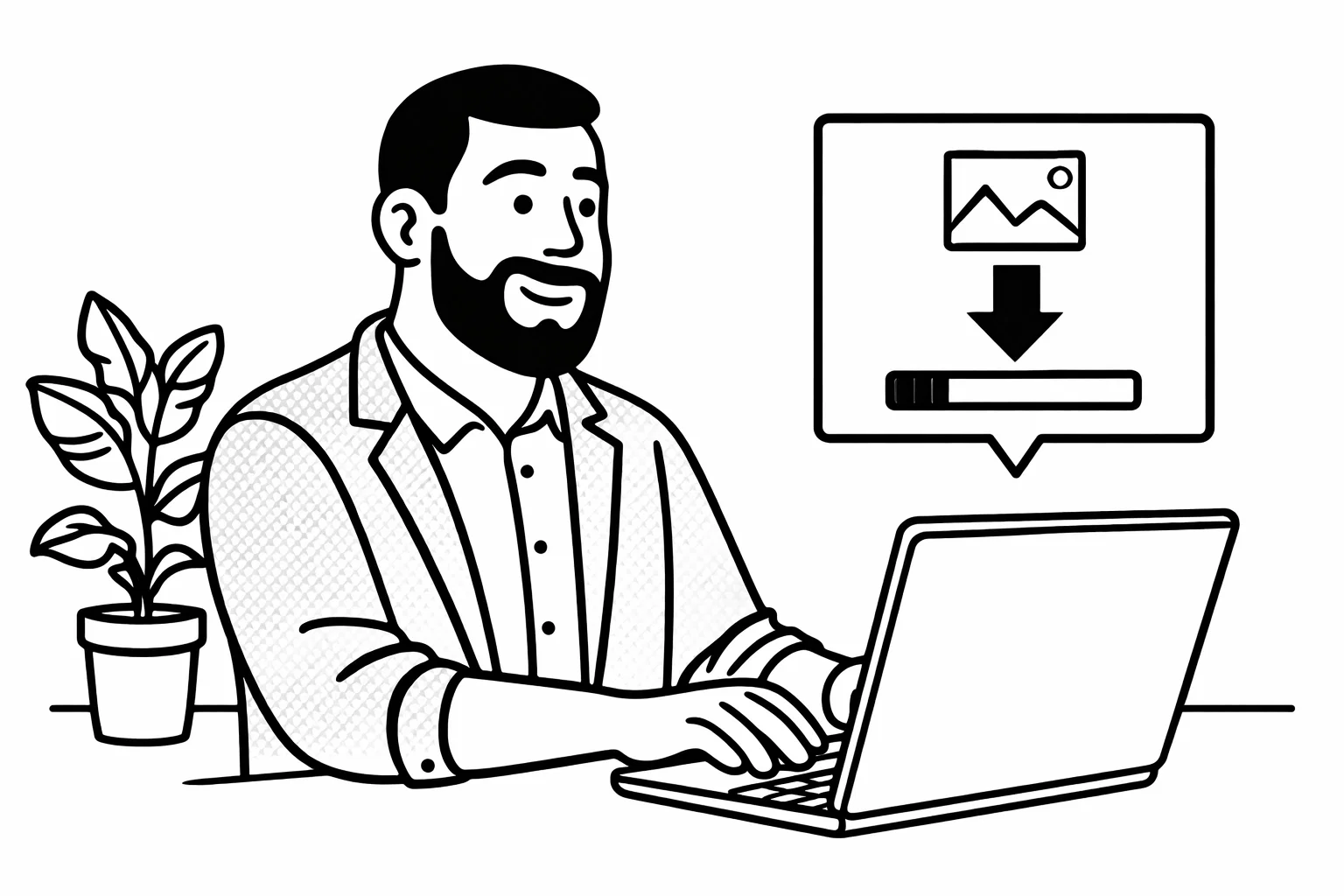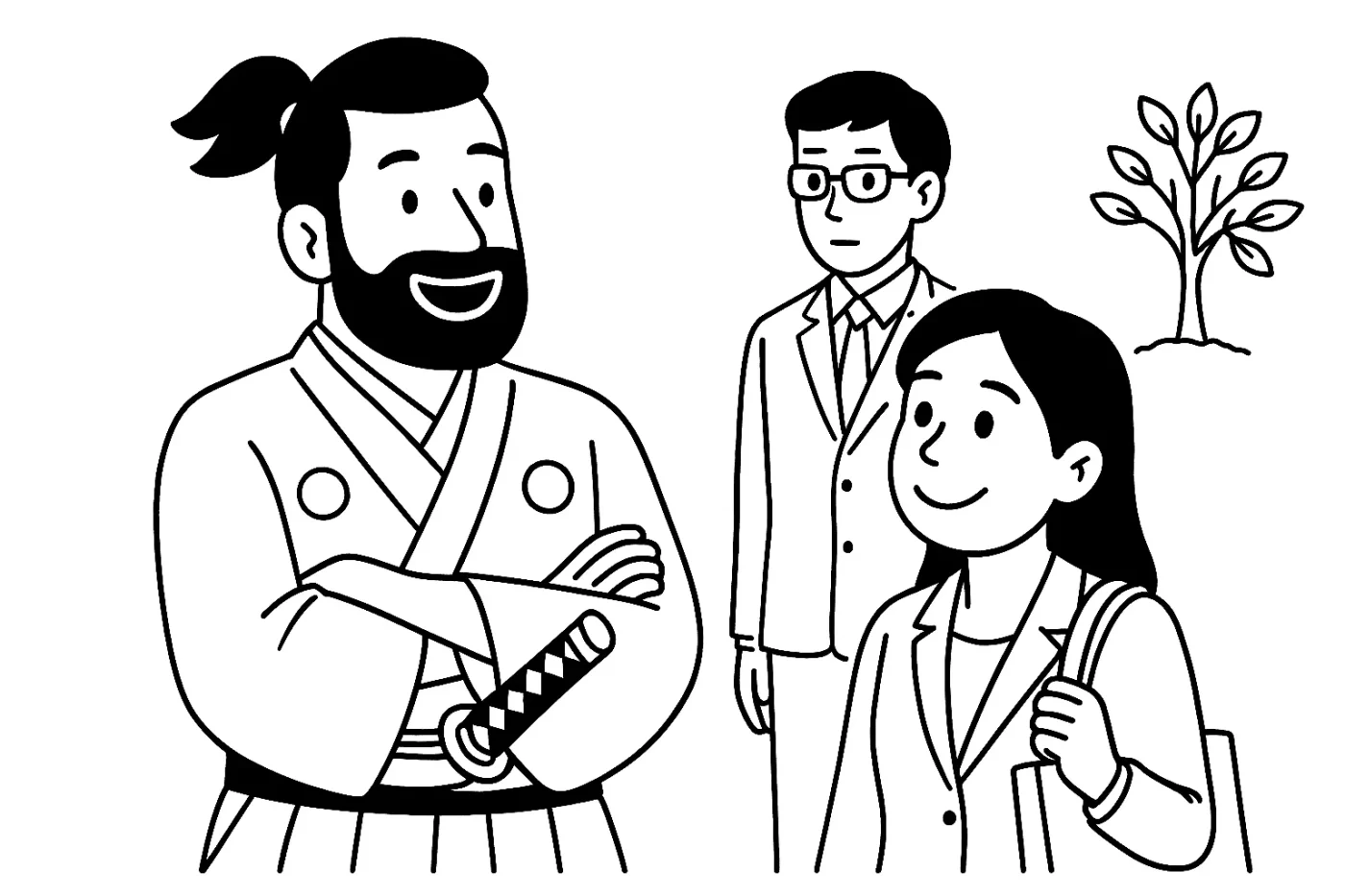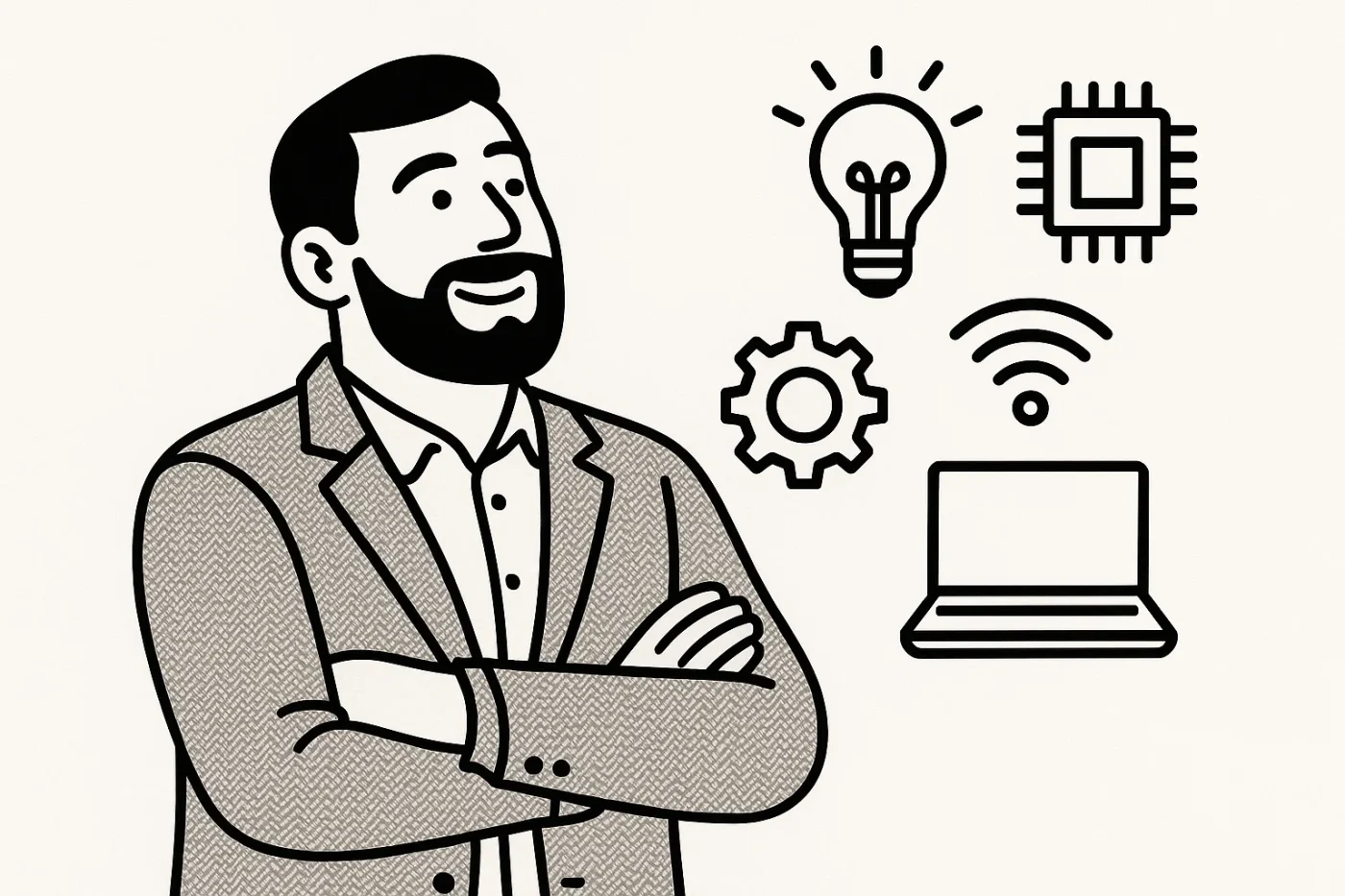まずは「仮想社員」を一人雇う感覚で
AIを導入しようと考えたとき、「全部やらなければならない」と思うと気持ちが重くなってしまうことがあります。
私もそうでした。
ニュースではAIがなんでもできるかのように語られますが、実際に現場で活用しようとすると、どこから手をつけていいか分からず、途方に暮れてしまうのです。
でも、よく考えてみると、最初から全部やらせる必要はありません。
まずは「仮想社員」を一人雇う感覚で、役割を一つ決めてみる。それだけで十分なのです。
小さな役割から始める
私は、まずAIに「メールの返信だけお願いする」というところから始めました。
次に、データをまとめて表を作ってもらいました。
その次は、プレゼン資料を作ってもらうようになりました。
このように、一つの役割に絞ると、指示も具体的になり、成果も見えやすくなります。
AIを相棒のように感じられるのは、こうして仕事を一緒に積み重ねるからだと気づきました。
圧倒的なコストパフォーマンス
さらに大きいのは、そのコストパフォーマンスです。
最低時給が1,000円を超えるこの時代、人に仕事を頼めば3,000円でお願いできるのはせいぜい3時間程度です。
しかし、AIはその3,000円で1ヶ月間、24時間ずっと働き続けてくれます。
一人の人に頼むには気が引けるような仕事も、遠慮なくAIに頼める。
そして、何度でもやり直してくれる。
この感覚は、一度体験すると手放せません。
まずは打席に立つ
AIに全部を任せようとするから、重くなる。
最初は「メールだけ」「表だけ」「資料だけ」──そのくらいでいいのです。
一人の仮想社員を雇うつもりで、特定の役割を与えてみる。
その一歩を踏み出せるかどうかが、これからの経営の分かれ道になると私は感じています。