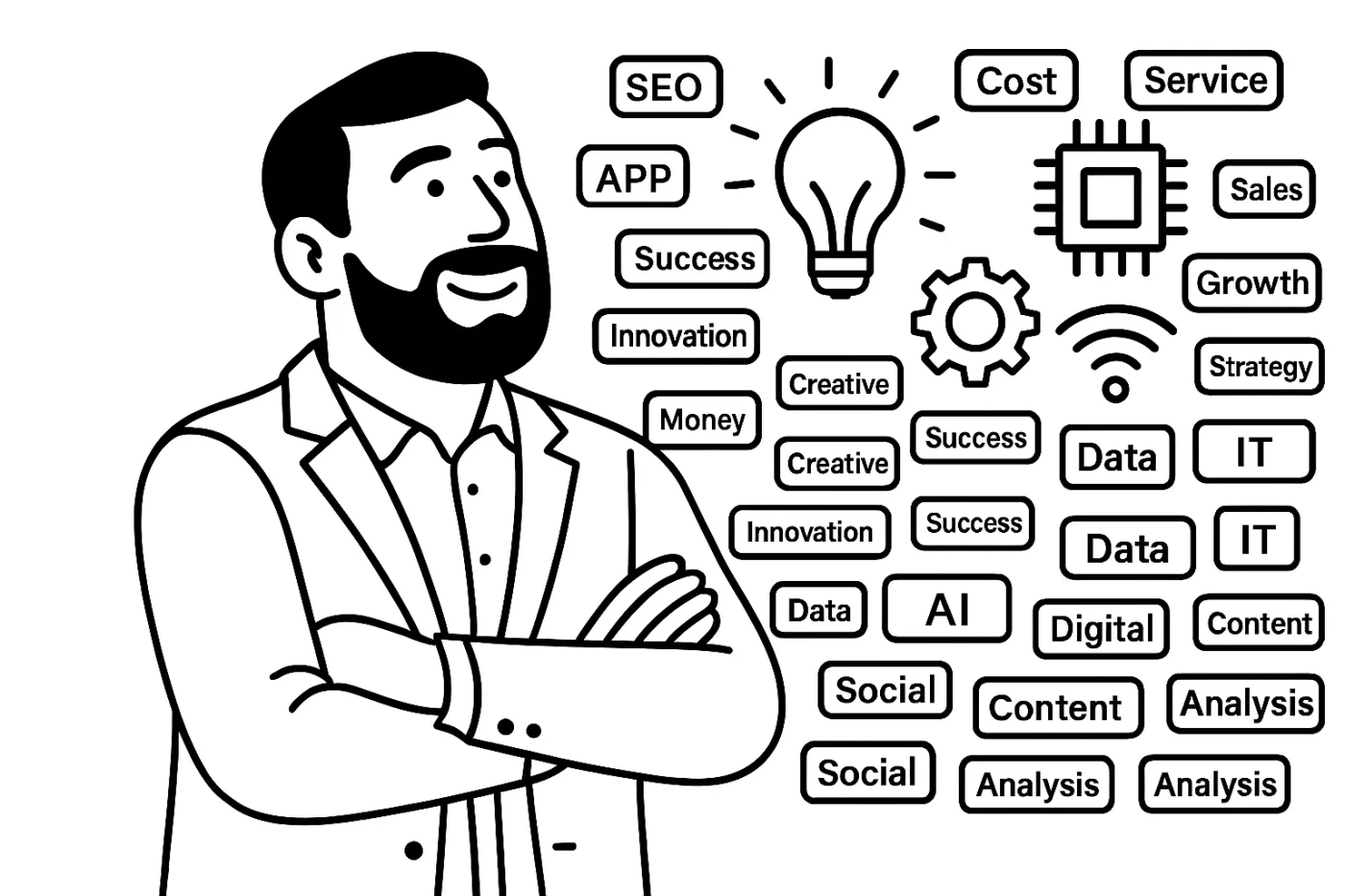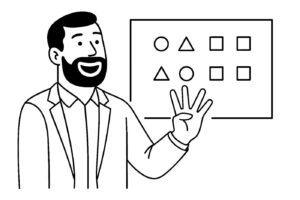発芽ブログの概要
「発芽ブログ」とは、一つのテーマを「種」として捉え、そこから国語・算数・理科・社会といった多様な切り口で創造性を広げ発信するアプローチです。
また、4教科で広げたアイデアは『逆転の発想』でさらに創造性を深められます。
このように、身近な体験や小さな気づきを出発点に、記事のアイデアを次々と展開していくことが特徴です。
発芽ブログは、SEOや集客を目的とするのではなく、書くこと自体を楽しみながら思考の柔軟性を育てたい個人ブロガーや、創造性を高めたい学習者に特におすすめのアプローチです。
名前の由来
種から芽が出て育っていくように、ひとつのテーマから複数の記事が派生し、やがて体系的なコンテンツの森ができあがります。
「発芽ブログ」という名前は、この自然な広がりをイメージして名付けました。

特徴とメリット
- ネタ切れを防ぐ:小さな種が多彩な記事群に広がるため、常に発信を続けられる。
- 創造性の向上:書き手自身の思考が柔軟になる。
具体例
例えば「電車のポスター1枚」をテーマにした場合:
- 国語 → キャッチコピーの分析
- 算数 → 広告費や利用者数の計算
- 理科 → 紙やインク、印刷技術の話
- 社会 → 鉄道文化や広告産業の歴史
こうして一つのテーマから、まるで芽が次々と出てくるように複数の記事を展開していけます。

有限会社ビーアイティーと発芽ブログ
この手法を体系化し提唱しているのが 有限会社ビーアイティー です。
当社では「発芽ブログワークショップ」を開催し、参加者が実際にこの手法を体験できる場を提供しています。
複数サイト運営での実務的メリット
発芽ブログの発想は、複数のメディアサイトを運営する場合に特に効果を発揮します。
従来の複数サイト運営の課題
以前は専門性の高い複数サイトを運営しようとすると、それぞれ独立した取材や情報収集が必要で、時間とコストが大幅に増加していました。ビジネス系サイト、教育系サイト、地域情報サイトを運営するなら、それぞれ別々の取材が必要で、現実的ではありませんでした。
発芽ブログによる効率化
しかし発芽ブログの手法を使えば、一回の取材や体験から複数サイト用のコンテンツを同時に生み出すことが可能になります。例えば、一つの企業取材から:
- ビジネスサイト:経営戦略の視点で記事化
- 教育サイト:人材育成の観点で記事化
- 地域サイト:地域経済への影響で記事化
このように展開することで、取材コストを抑えながら各サイトの専門性を維持できます。
SEO面での利点
単一サイトでの発芽ブログは専門性の希薄化というリスクがありますが、複数の専門サイトでの展開なら各サイトの専門性を保ちつつ、更新頻度も維持できるため、SEO的にも理にかなったアプローチとなります。
ただし、この手法も各サイトの方向性やターゲット読者が明確でないと、結果的にどのサイトも中途半端になるリスクがあります。複数サイト運営には、それぞれのサイトの位置づけを明確に管理する運営力が前提となります。
発芽ブログの注意点:理想と現実のバランス
発芽ブログは確実にネタ切れを防ぎ、書き手の思考を柔軟にする効果がありますが、一方で注意すべきリスクも存在します。
専門性の希薄化
一つの体験から複数の分野に記事を展開することで、どの分野でも専門家レベルの深さに達しない可能性があります。カフェでの体験から心理学、ビジネス論、地域情報まで扱った結果、どの記事も表面的な内容に留まり、その分野の専門家や深い知識を求める読者には物足りない内容になってしまうリスクです。
検索ニーズとのミスマッチ
読者の具体的な検索意図と記事内容がずれてしまう傾向があります。「○○区 カフェ」で検索して来た読者が心理学の話を読まされたり、「集中力 向上」で来た読者にカフェの店舗情報が混じったりと、読者が求めている情報と提供している情報のギャップが生じやすくなります。
SEO・集客面での限界
GoogleのE-A-T(専門性・権威性・信頼性)評価において、多分野を浅く扱うサイトよりも、一つの分野を深く掘り下げたサイトの方が高く評価される傾向があります。発芽ブログは結果的に「雑記ブログ」の性質を持つため、特定のキーワードでの検索上位表示や安定的な集客には向かない可能性があります。
適切な活用法 これらの限界を理解した上で、発芽ブログは以下の目的で活用することをお勧めします:
- ネタ切れ防止の手法として
- 思考の柔軟性を鍛える訓練として
- 純粋に書くことを楽しむためのアプローチとして
集客やSEOが主目的の場合は、より専門性に特化した別の手法を検討することが現実的です。
発芽プロジェクトのワークショップは大阪市中央区南船場のオフィスで開催しています。無料で参加可能ですので、ご希望の曜日と時間帯を選んでお申込みください。
発芽ブログ一覧

-

Weconomy(我々経済)とは何か|「Meconomy」から「我々欲」へ
「Weconomy(ウィコノミー)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。“私たち(We)”と“経済(Economy)”を掛け合わせた造語であり、21世紀の資本主義の限界を超える新しい潮流を象徴している。 私はこの言葉を日本語に訳すとき、こう呼びたいと思った。... -



累積コストではなく、累積削減だ|マイナポイント3万円のROI 589.8%を検証する
「毎年3万円を配るなんて、国の財政がもたない」――そう感じた人も多いだろう。 しかし、数字で検証すると、見えてくる世界はまったく違う。 ※本稿は、前稿「我々欲マイナポイント制度」に基づく財政的検証篇です。制度の思想的背景や全体構造については、... -



住民税の境界を超えるとき|関係人口と憲法が示す“我々欲”の新しい自治
少子高齢化が進み、地方と都市の格差が広がるいま、「住んでいるところの税金はその地域だけで使う」という前提が、静かに崩れ始めている。関係人口という言葉が示すように、人と地域の関わり方は多層化している。この変化をどう制度に落とし込むか。その... -


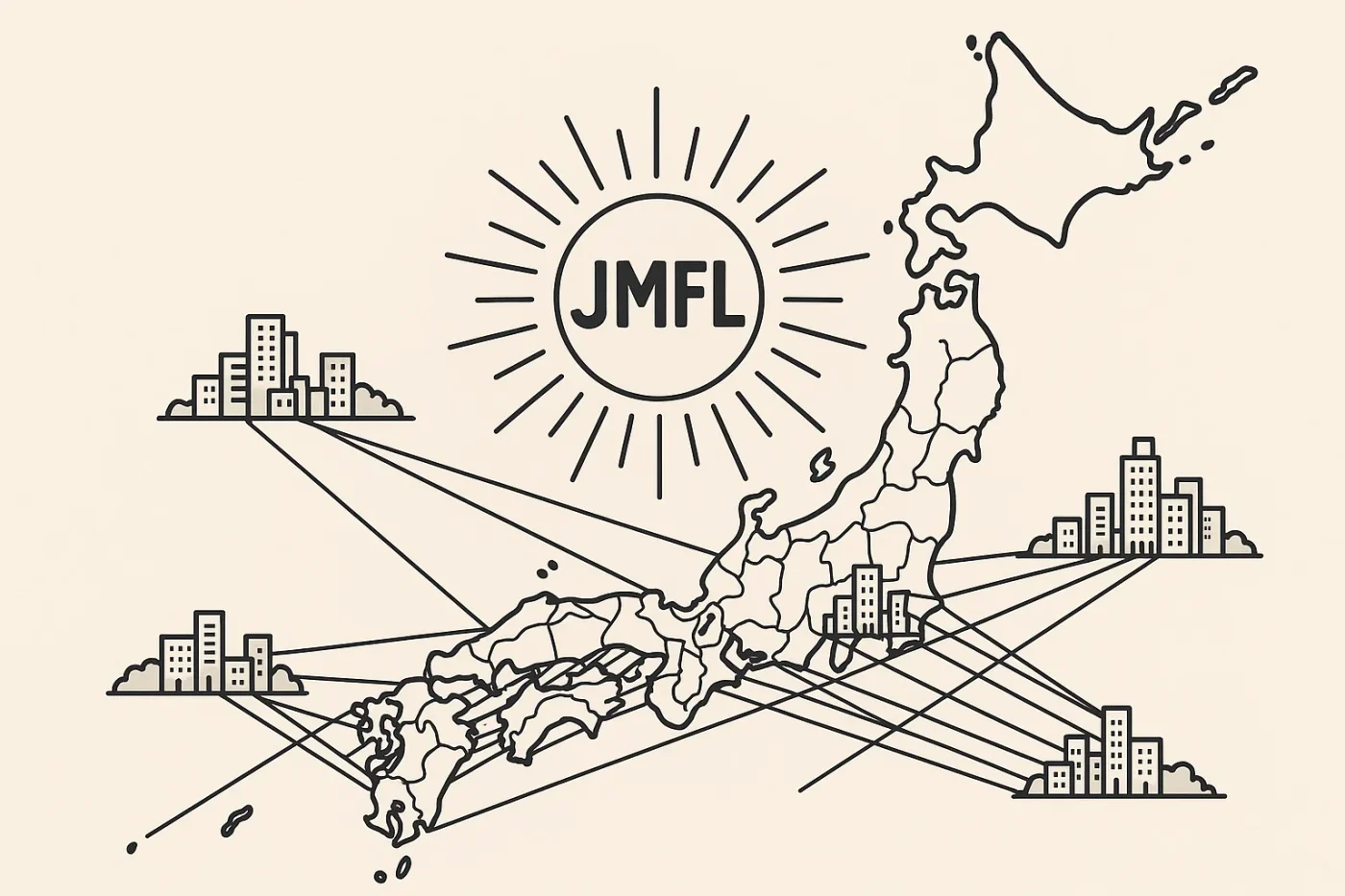
我々欲マイナポイント制度〜スポーツリーグに学ぶ自治体間財政調整の新しい形〜
ふるさと納税をブーストする次世代の地方創生 提言者:夫 太男作成日:2025年10月22日 第1章:日本が直面する危機 1-1. 東京一極集中の加速 日本は世界でも稀に見る「一極集中国家」です。 東京圏(1都3県)の人口: 約3,700万人 日本の総人口の約30% 世... -


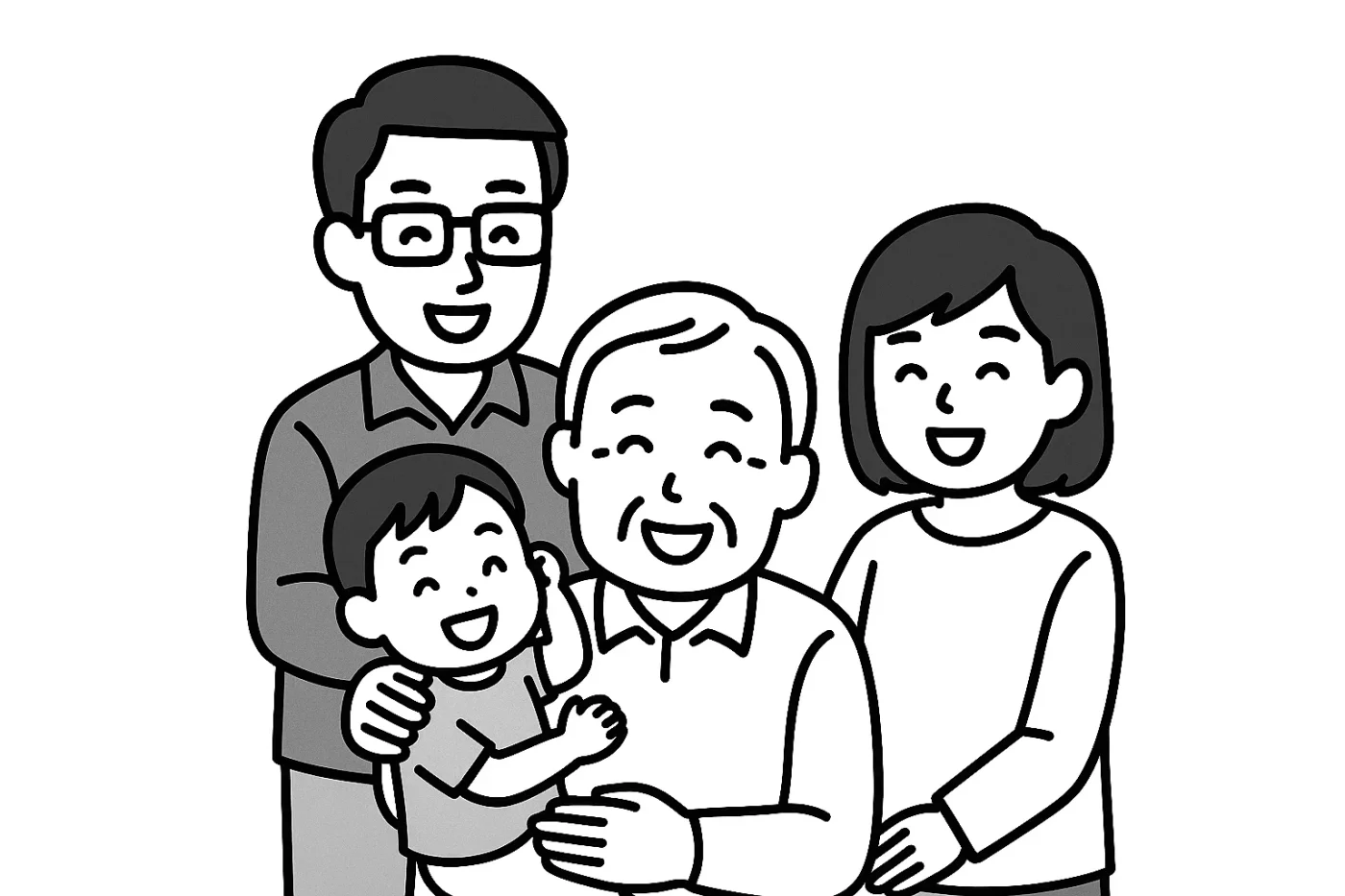
日本の少子化を解決する「祖父母育て」という選択肢
少子化、教育費高騰、共働き疲弊──これらの社会課題を、経済・文化・制度・心理の多面から読み解く「発芽メソッド」の視点で考察する。ここで提案するのは、家族の再設計ともいえる「祖父母育て」モデルである。 疲弊する日本の家庭──ある夫婦の朝 「子ど... -


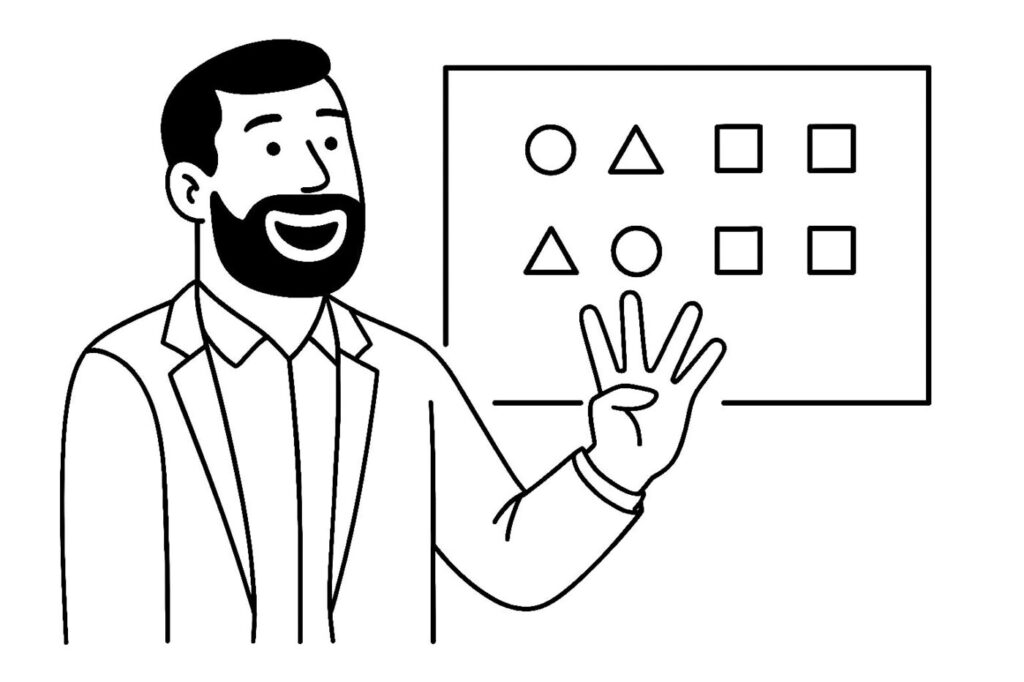
応用編|発芽ブログ 脱4教科で新たな4視点の応用
発芽ブログの基本は「国語・算数・理科・社会」の4教科で記事を整理することでした。 この型はシンプルでわかりやすく、誰でもすぐに使える入り口です。 発芽ブログについてはこちら▼ https://bit.gr.jp/hatsuga-blog/ けれども、書き慣れてくると「もう少... -


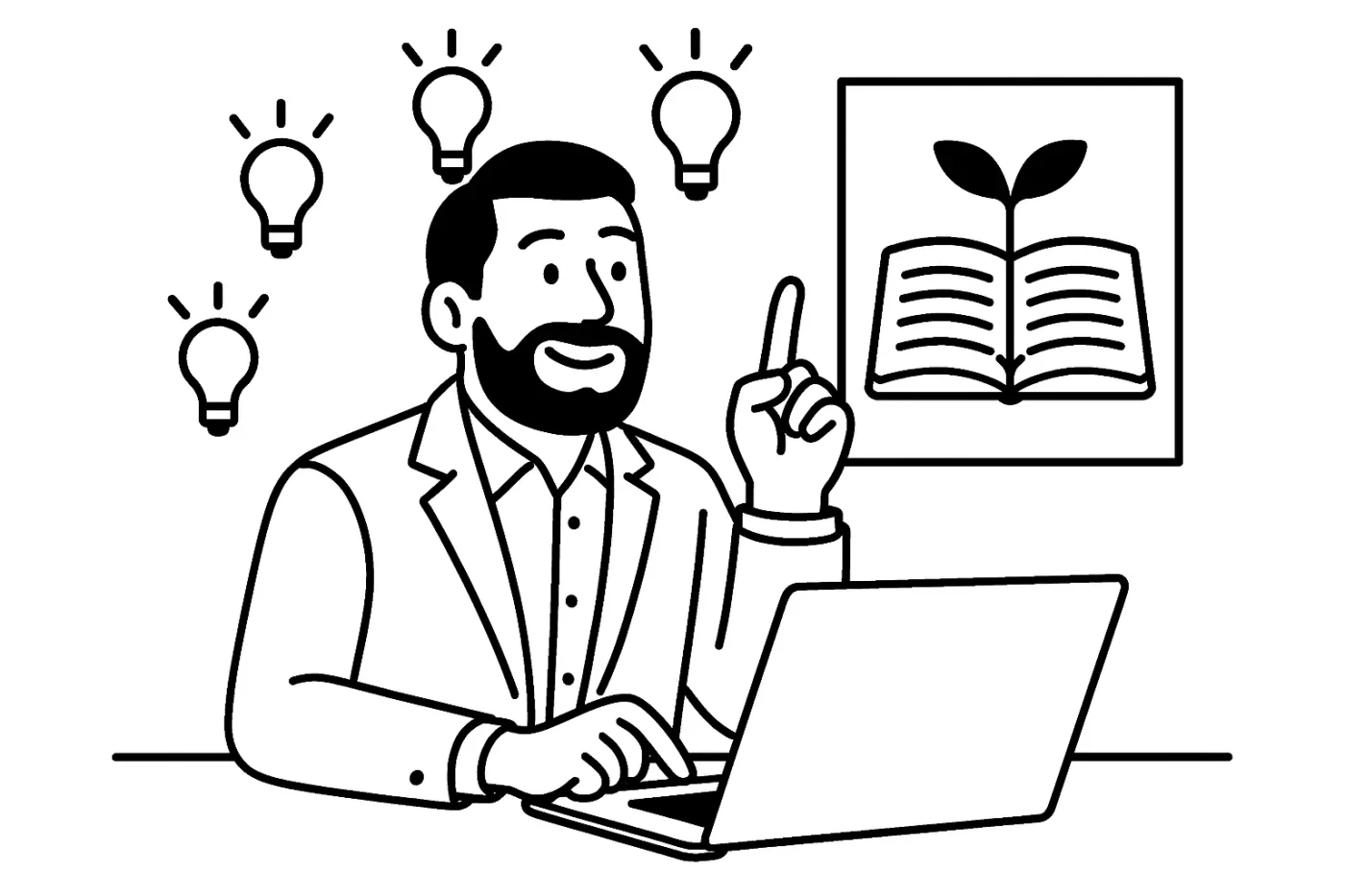
発芽メソッド:1つのものから無限の価値を見出す多面的思考法
「この商品、もっと活かせる方法はないだろうか」 「一つのテーマから、もっと多くの可能性を見つけたい」 そんな思いを抱く零細企業経営者のために開発されたのが「発芽メソッド」です。 発芽メソッドとは 発芽メソッドとは、1つのテーマや商品を「国語・... -


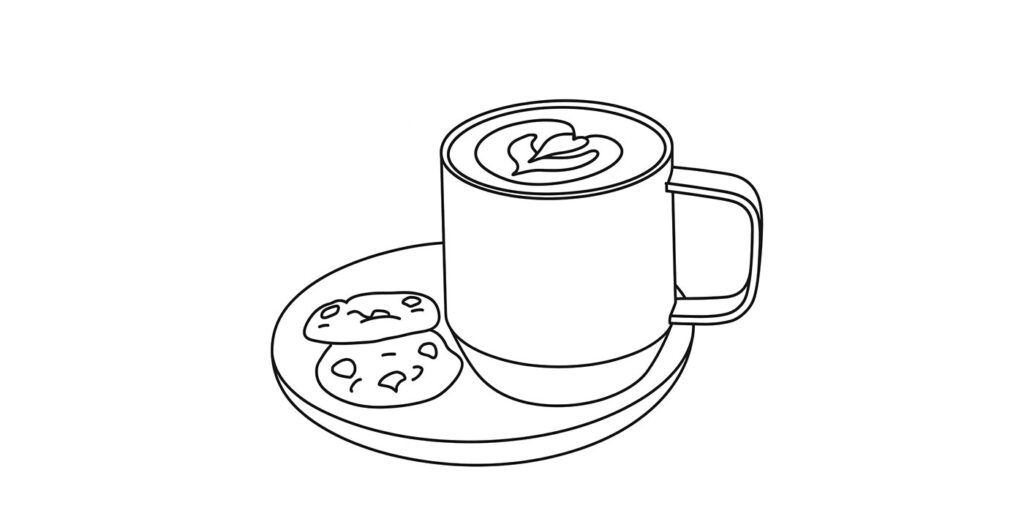
フィーカップから広がる学びの世界
【発芽メソッド実践者・学習者の皆さまへ】 「発芽メソッドの手法は理解できたけれど、実際にクライアント案件でどう活用すればいいの?」 「商品紹介記事に4教科アプローチを取り入れる具体例が見たい」 「ワークショップで学んだことを、実践でどう展開... -


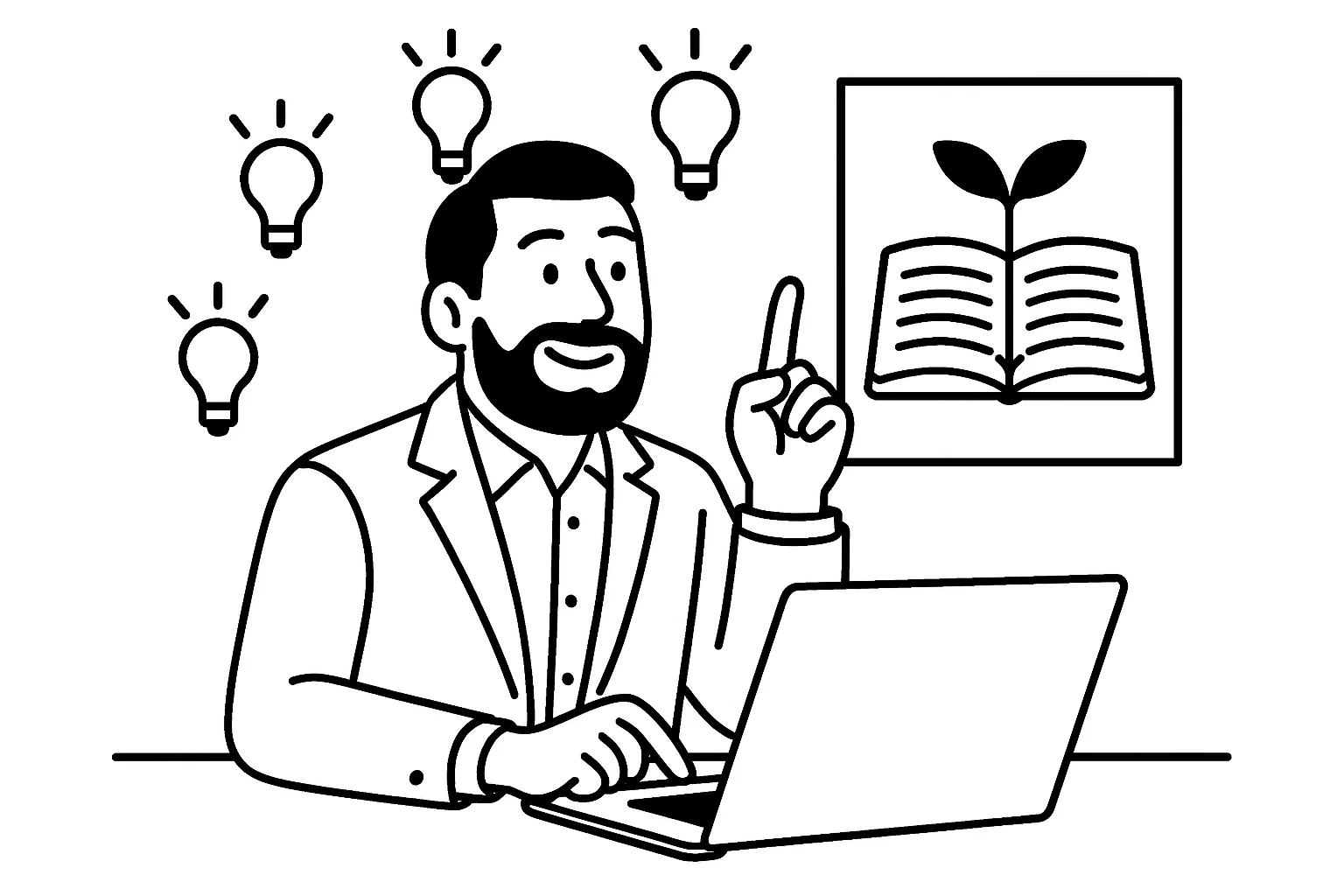
発芽ブログとは|一つのコトから創造性を広げるアプローチ
発芽ブログの概要 「発芽ブログ」とは、一つのテーマを「種」として捉え、そこから国語・算数・理科・社会といった多様な切り口で創造性を広げ発信するアプローチです。 また、4教科で広げたアイデアは『逆転の発想』でさらに創造性を深められます。 この... -


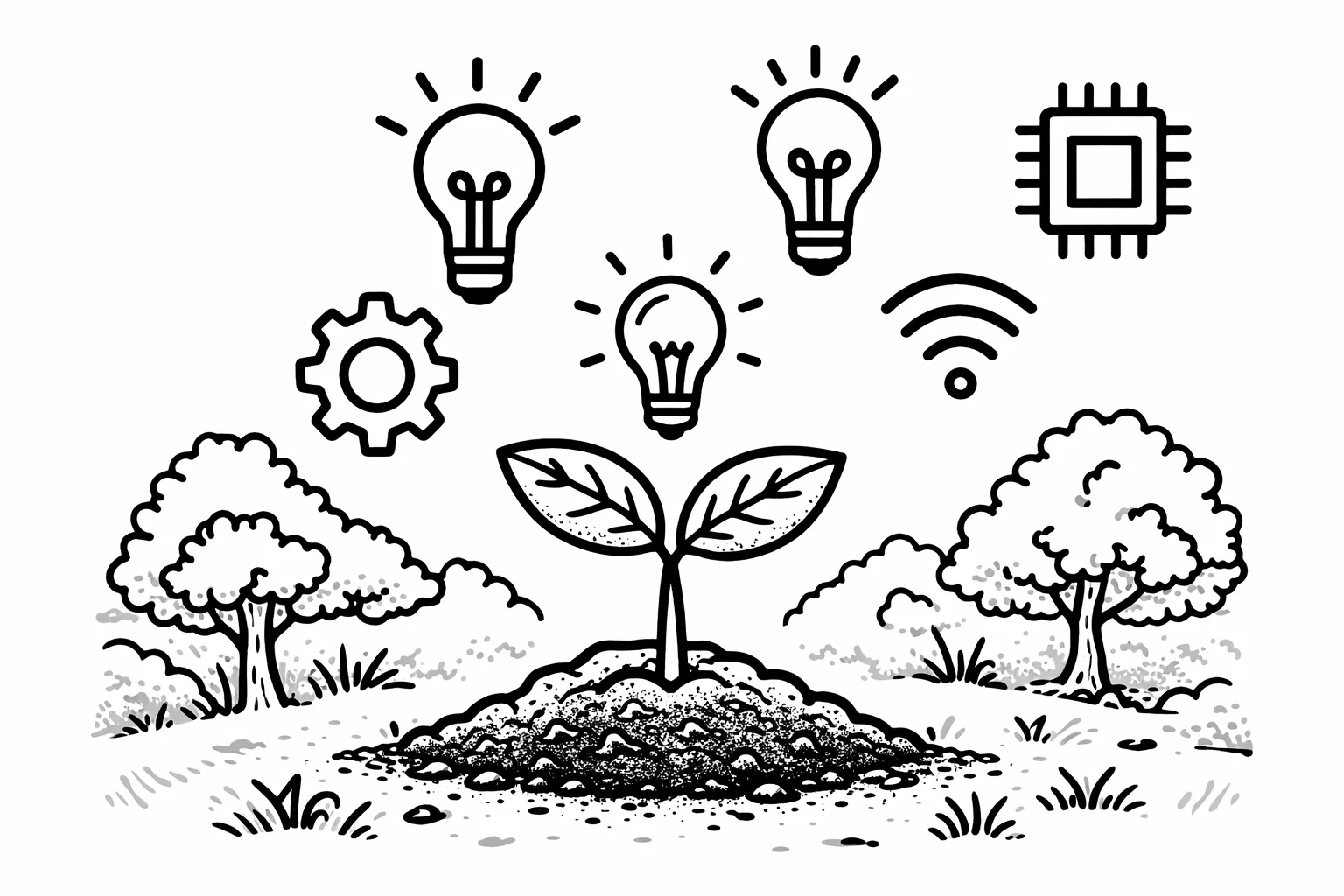
発芽ブログのコツ:テーマを決めて日常にアンテナを張る方法
電車のポスター1枚から4回連載記事が生まれるまで 普段車移動の経営者が電車で発見したもの 経営者や専門職にとって、効率的かつ独自性のある情報収集は常に課題となります。そのヒントは、意外にも日常の中に潜んでいることもあるのです。たとえば筆者の...