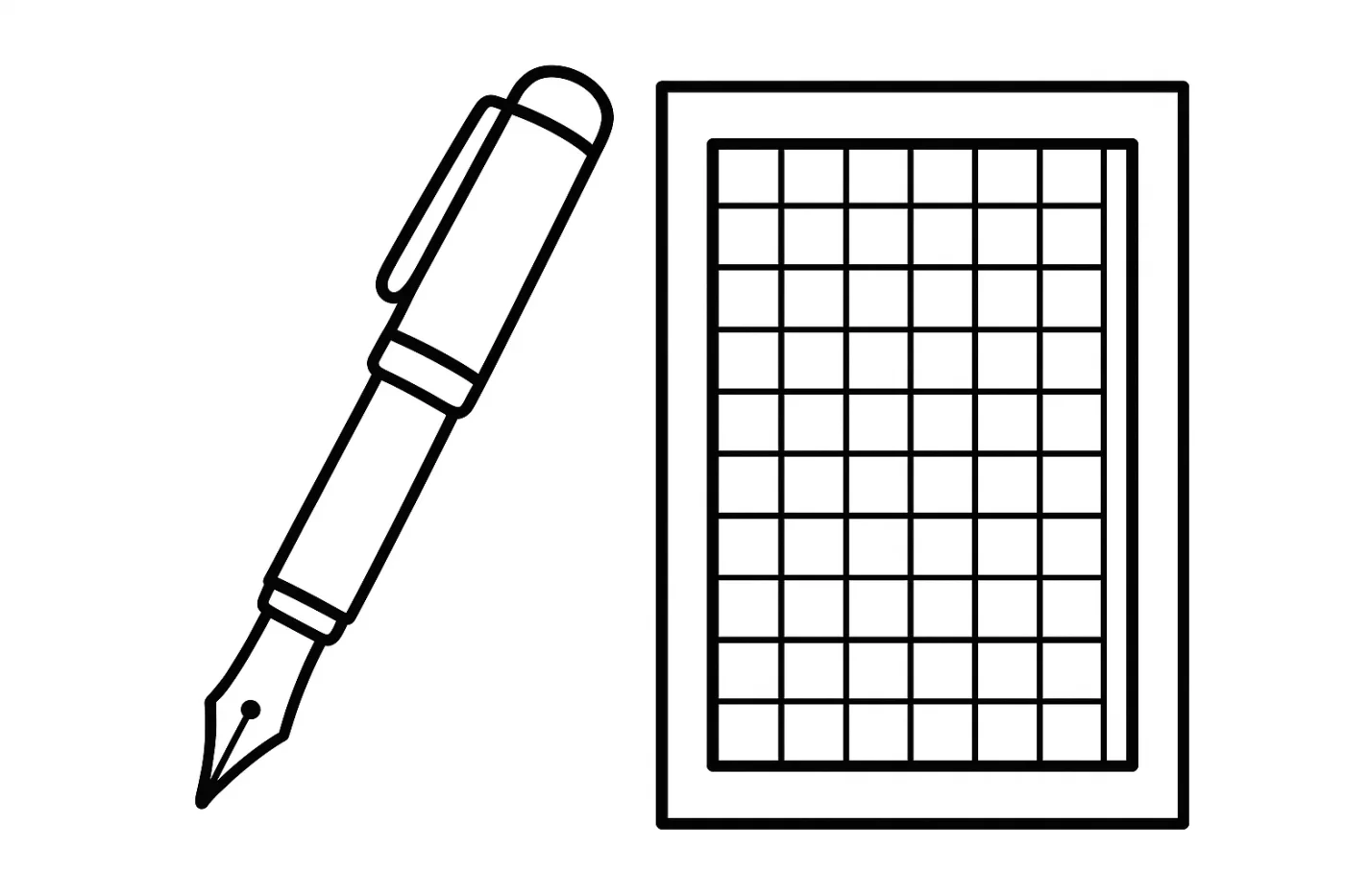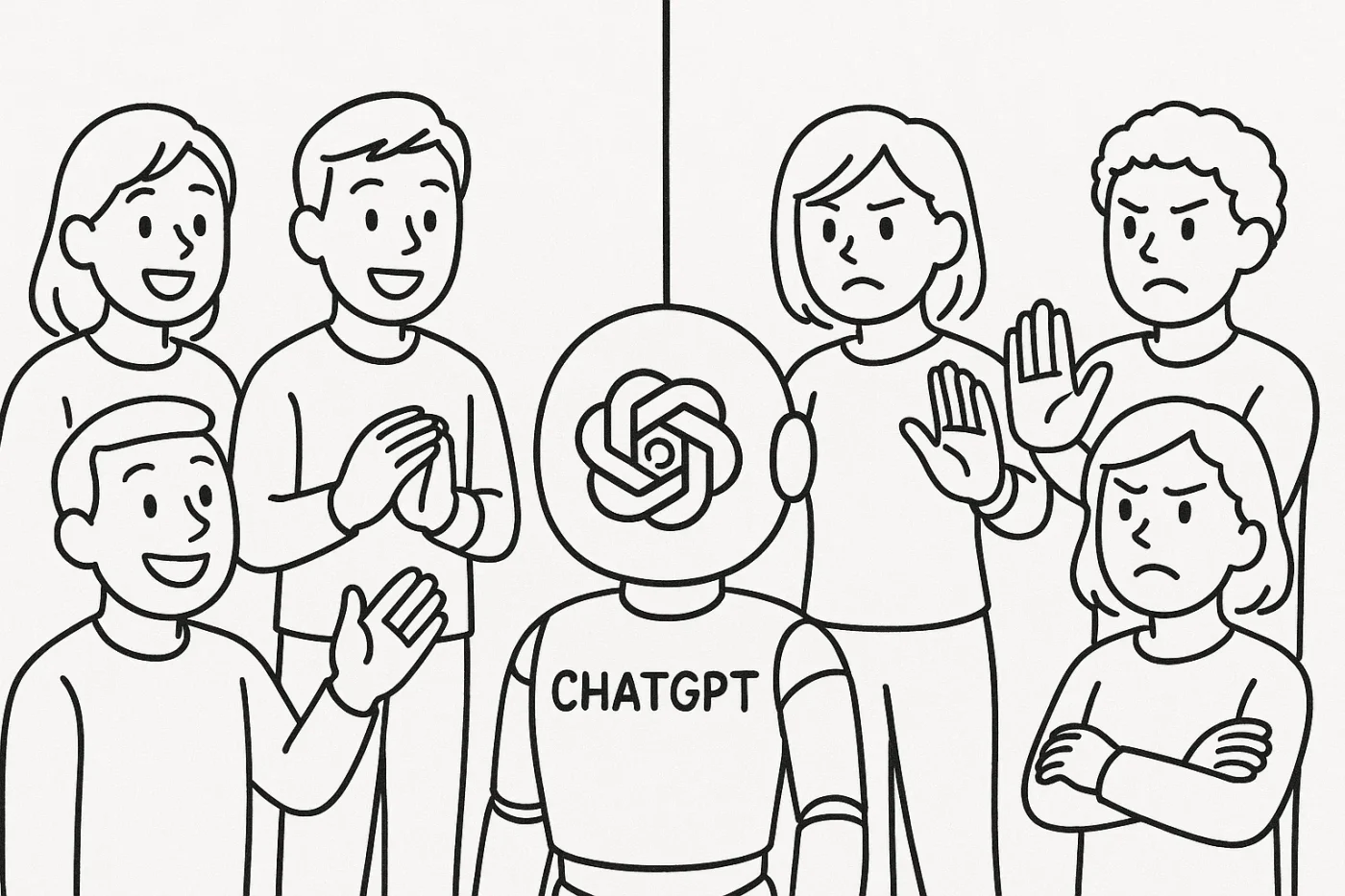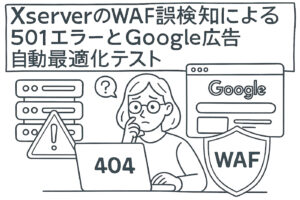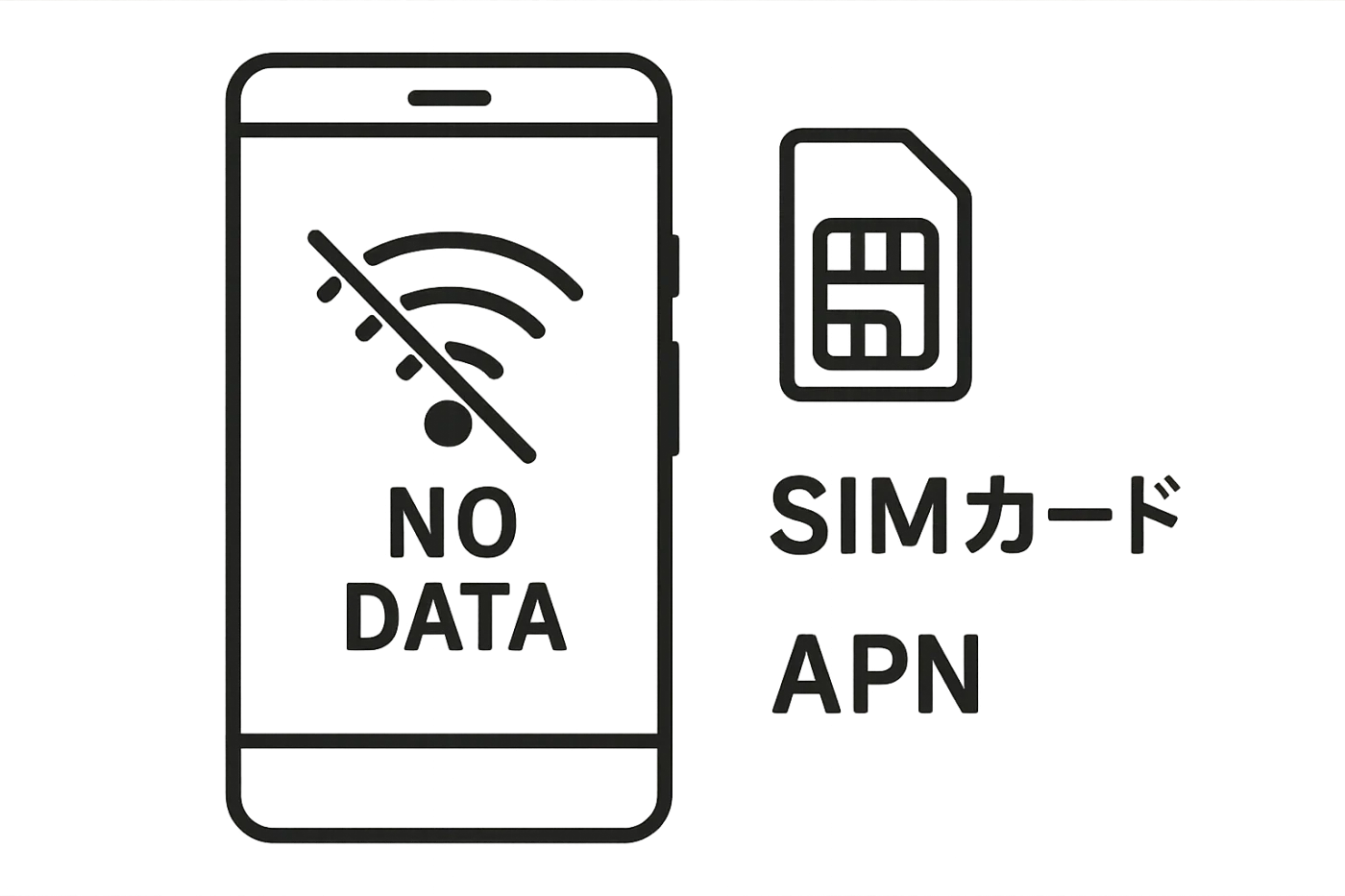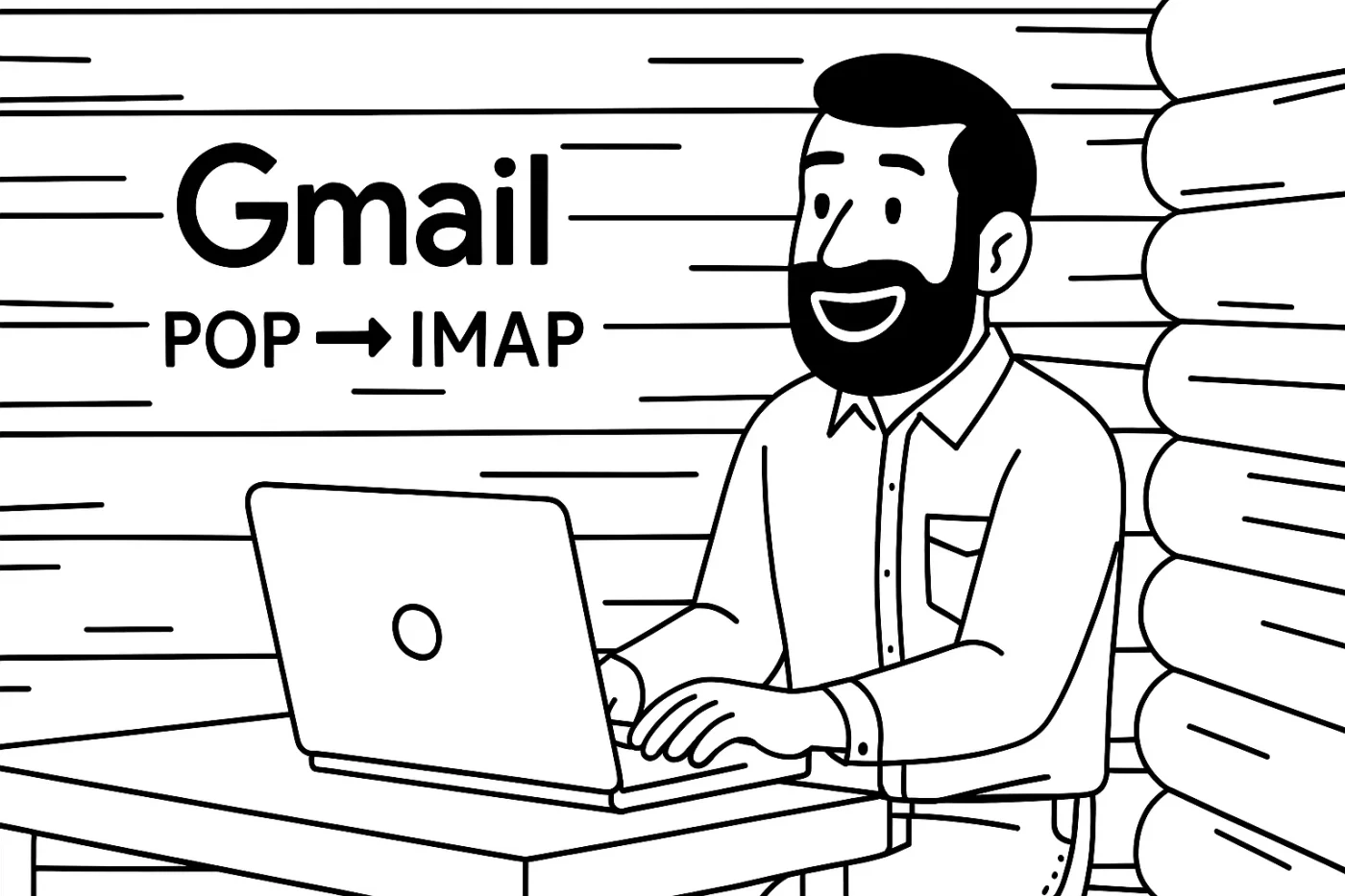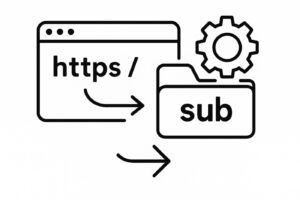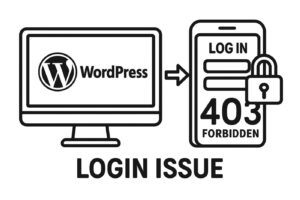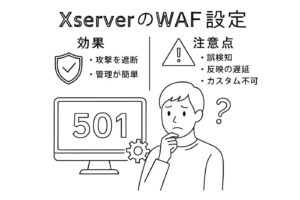はじめに
AIを活用してブログを効率的に書くためには、ツールに頼るだけでなく、日常の思考や行動そのものを“ブログモード”にしていくことが大切です。この記事では、実際に多くの執筆者が実践している「8つのステップ」に分けて、AIと共にブログを習慣化するためのヒントをまとめました。
ネタは“ストックする習慣”で生まれる
日常生活やSNS、広告の中には、記事のヒントがたくさん隠れています。アイデアは「考えてひねり出す」より、「見つけたらメモする」ほうが効率的。スマホのメモアプリやNotionなどで、気になる言葉や話題をストックしておきましょう。
キーワードリサーチで「求められる内容」を探す
思いついたネタをそのまま記事にするのではなく、Googleの検索サジェストやキーワードプランナーなどを使って、「どんな言葉で検索されているか」を調べてみましょう。読者のニーズに寄り添う視点が、読まれる記事を作る第一歩になります。
ペルソナは“友達”ぐらいがちょうどいい
年齢・性別・職業などを細かく決めすぎると手が止まりがち。書くときは、「あの友達に話しかけるつもり」で十分。たとえば「ブログ初心者の後輩に説明する感じ」など、書き手のリアルな感覚を大切にしましょう。
構成を組んでから本文に取りかかる
書き出す前に、見出し(H2・H3)で全体の構成を組み立ててみましょう。「結論 → 理由 → 具体例 → 再結論」という流れを意識すると、読者にとっても理解しやすく、書き手にとっても迷わない文章になります。
結論から書くスタイルでスピードアップ
冒頭でいきなり「この記事で言いたいこと」を伝えてOKです。説明があとからでもついてくるなら、読者は安心して読み進められます。「どうしてそう言えるのか?」という問いを本文で自然に解説する形にしていきましょう。
言葉はやさしく、見た目はシンプルに
読みやすさのコツは、「漢字を減らす」「ひらがなを活かす」「専門語はかみ砕く」こと。そして、改行や箇条書き、表組みなども使って、パッと見て理解しやすいレイアウトを意識しましょう。
完璧じゃなくても、まず投稿!
ブログ記事は「60点で出して、あとから直す」くらいでちょうどいい。AIの力で下書きを加速できる今、完成を待っているより、先に出して反応を見るほうが効率的です。公開後のリライトも積極的に行いましょう。
投稿前に「一晩寝かす」ことで客観視
書き終えたら、すぐに投稿せず、少し時間を空けてから見直すのがオススメです。誤字脱字や余計な言い回しに気づけるだけでなく、「本当にこの内容で伝わっているか?」を客観的に確認できます。
おわりに
AIに任せる部分が増えるほど、「何を書くか」「誰に届けるか」は人間の直感や感性が鍵になります。日々の行動がネタになり、1記事ごとに書き方が洗練されていく。そうして“書ける人”になっていく過程こそが、AI時代のブロガーの成長そのものです。
発芽ブログシリーズはこちら▼

関連記事や参考になりそうなブログはこちら: