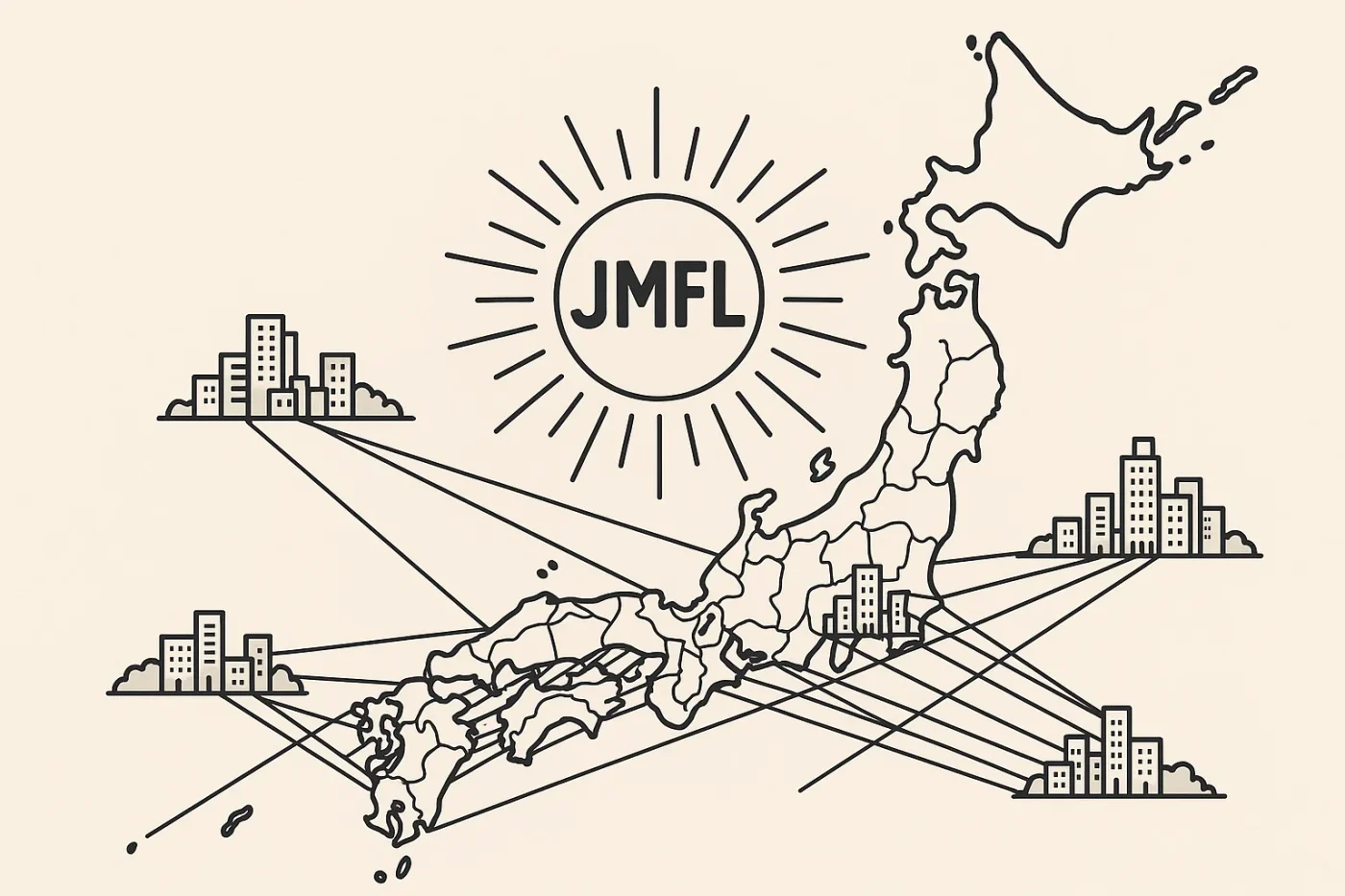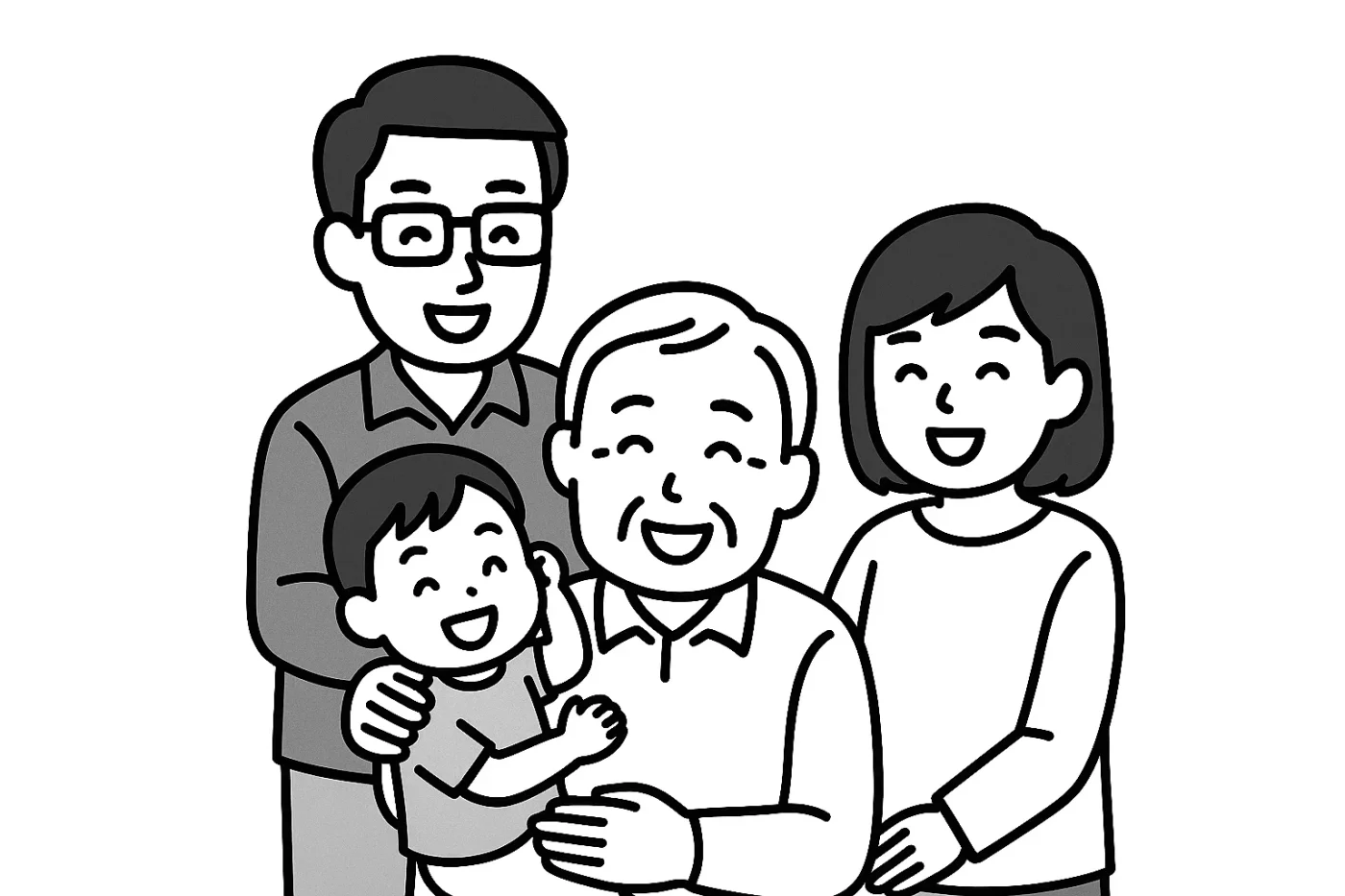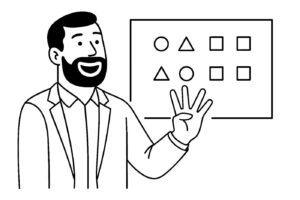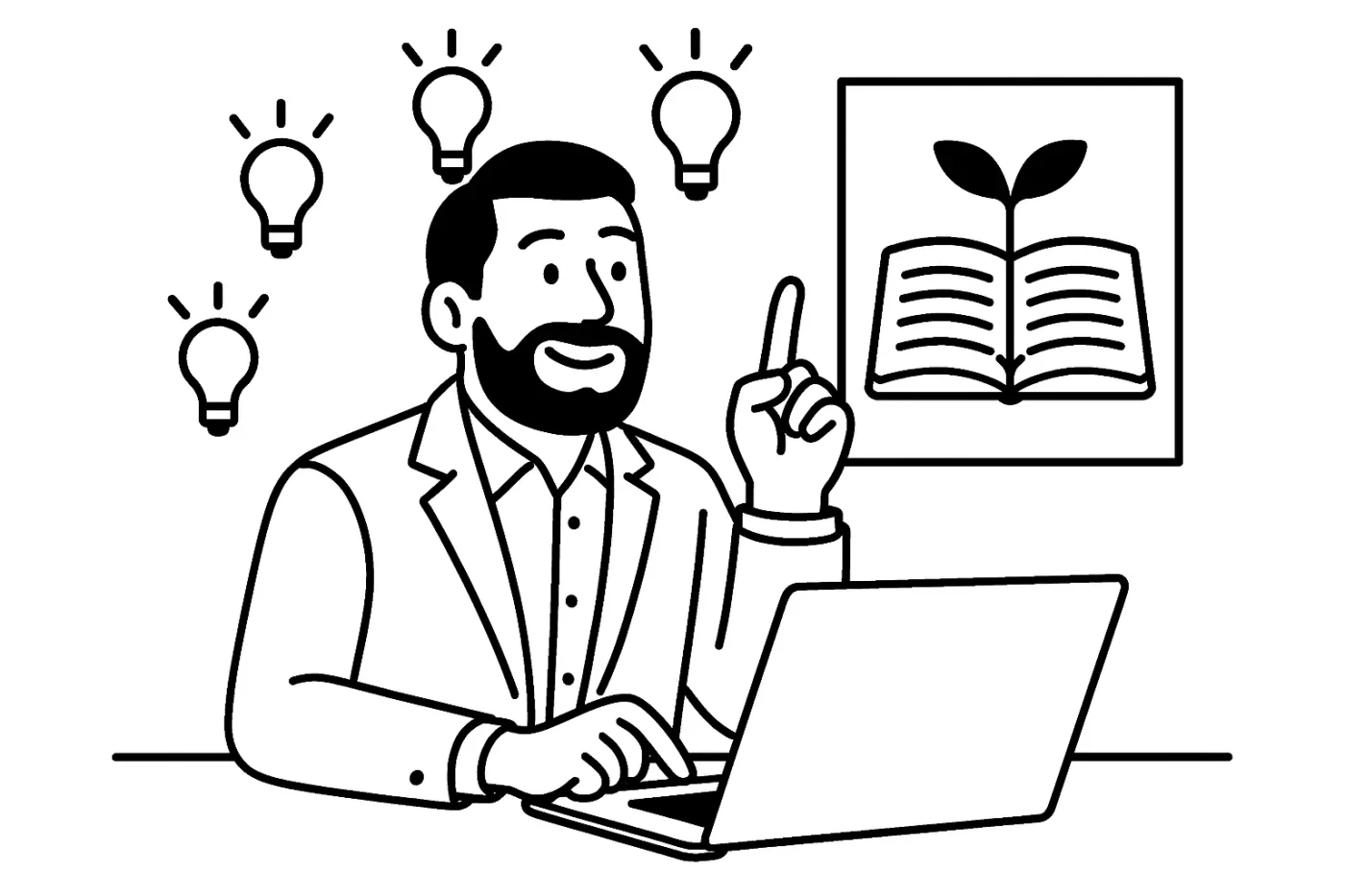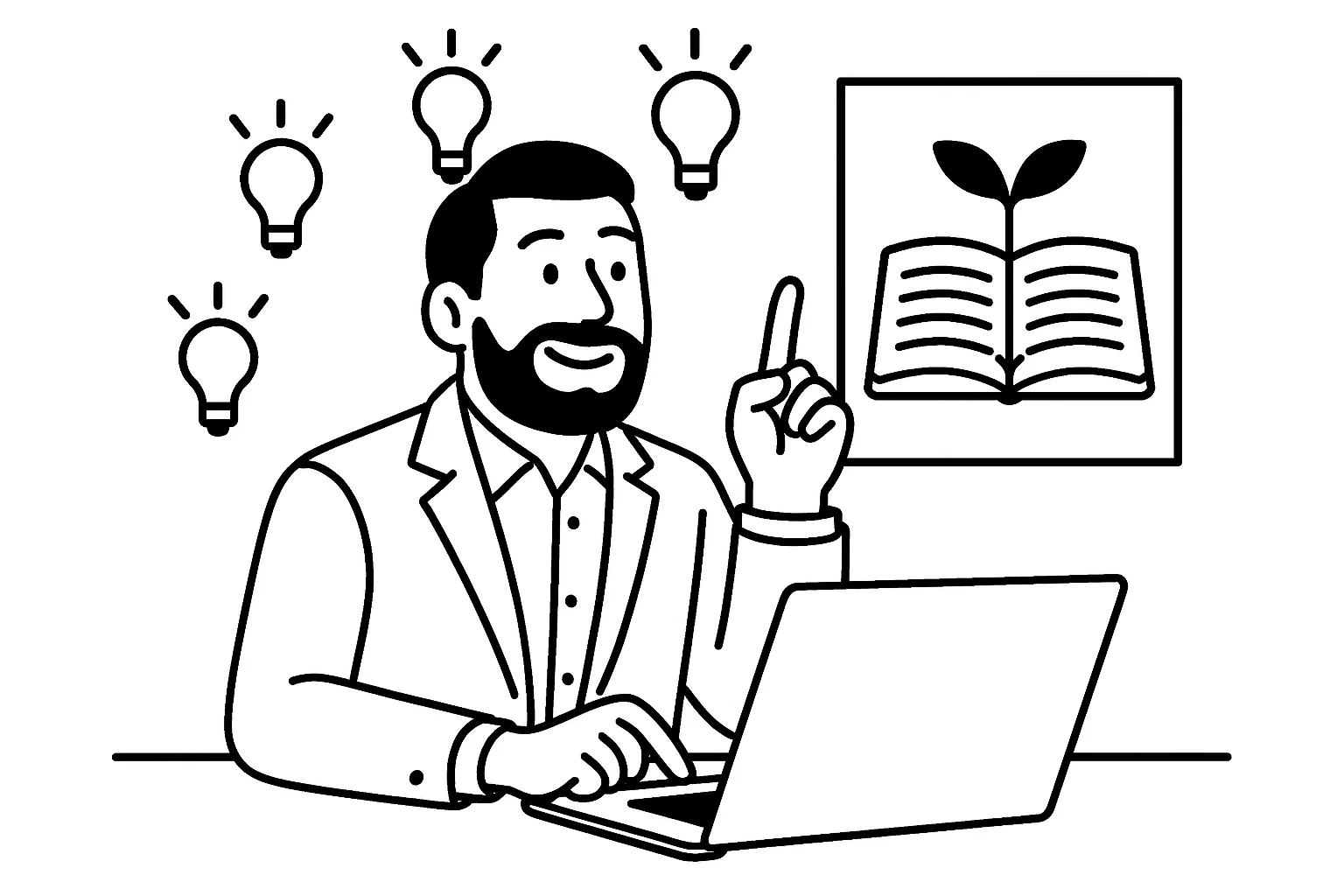少子高齢化が進み、地方と都市の格差が広がるいま、
「住んでいるところの税金はその地域だけで使う」という前提が、静かに崩れ始めている。
関係人口という言葉が示すように、人と地域の関わり方は多層化している。
この変化をどう制度に落とし込むか。
その問いに対する一つの答えが、「我々欲マイナポイント制度」である。
憲法の「地方自治の本旨」は生きている概念
憲法第92条に定められた「地方自治の本旨」は、1946年の社会を前提にしている。
当時の「住民自治」は、居住者による地域運営を意味していた。
しかし、現代の日本では、「地域に関わるすべての人」こそが住民であるという再定義が必要だ。
従来の解釈
- 住民自治=その地域に住む人だけの自治
- 団体自治=自治体単独で完結する運営
現代的な解釈
- 住民自治=地域に関わる人すべての意思を反映する自治
- 団体自治=自治体間連携と支え合いを含む運営
「ふるさと住民登録制度」が示す未来
政府は2025年に「ふるさと住民登録制度」を創設予定だ。
これは、居住地以外の自治体に「ふるさと住民」として登録し、
住民税の一部を登録先自治体に納税できる仕組みである。
10年で1000万人の登録を目標とし、
実質的に「住民税の分割納税」を制度化する。
つまり、「我々欲マイナポイント制度」と同じ方向性の思想が、すでに政策レベルで動き出している。
少子高齢化が「住民の定義」を変える
人口減少が進み、地方の財政基盤は限界に近づいている。
これまでの「その地域に住む人が支えるモデル」はもはや成立しない。
地方が単独で生き残るのは不可能であり、
都市と地方が相互に支え合う「我々欲」的な構造が必要になる。
現代の「住民自治」と「団体自治」
- 住民自治:港区民が同意制により、自らの税の一部を地方支援に回す
→ 自ら選択することで自治意識が深化する。 - 団体自治:夕張市などが孤立せず、全国ネットワークの一員として再生する
→ 連携による持続可能性を実現する。
「自治」とは分断ではなく、関係をデザインする力へと進化している。
憲法解釈の現代的進化
憲法は固定された文ではなく、社会の変化に応じて“生きて”いる。
少子高齢化と関係人口の時代において、
「地方自治の本旨」を新しく読み替えることこそ、
憲法の理念を現代に活かす道だ。
従来の枠組みに固執することこそが、
「住民の福祉」と「地域の持続的発展」に反する。
結語
この国に暮らす一人として、
どこに生まれたかよりも、どう生きたいかで関わっていけたらいい。
「我々欲マイナポイント制度」は、その関わり方を制度として形にした試みである。
関連リンク